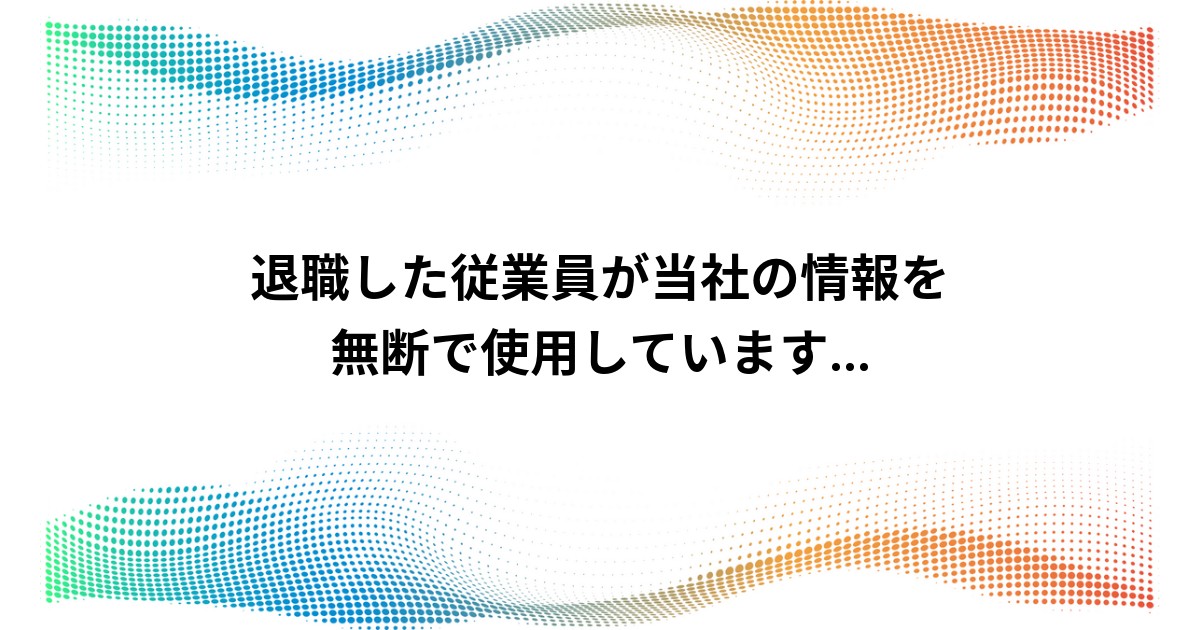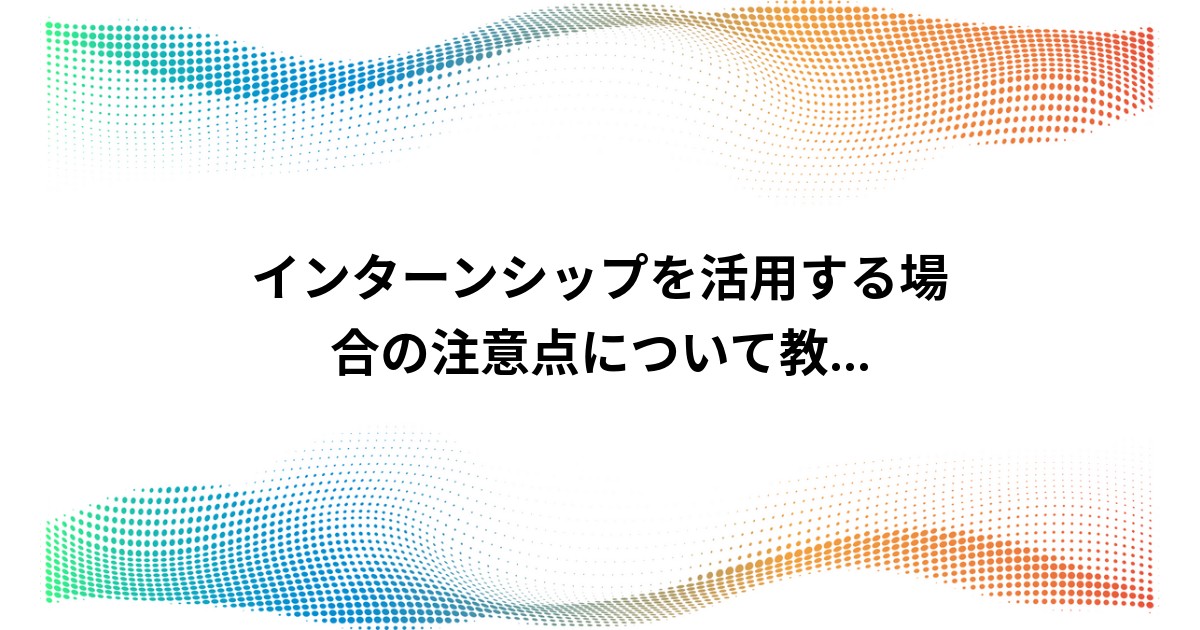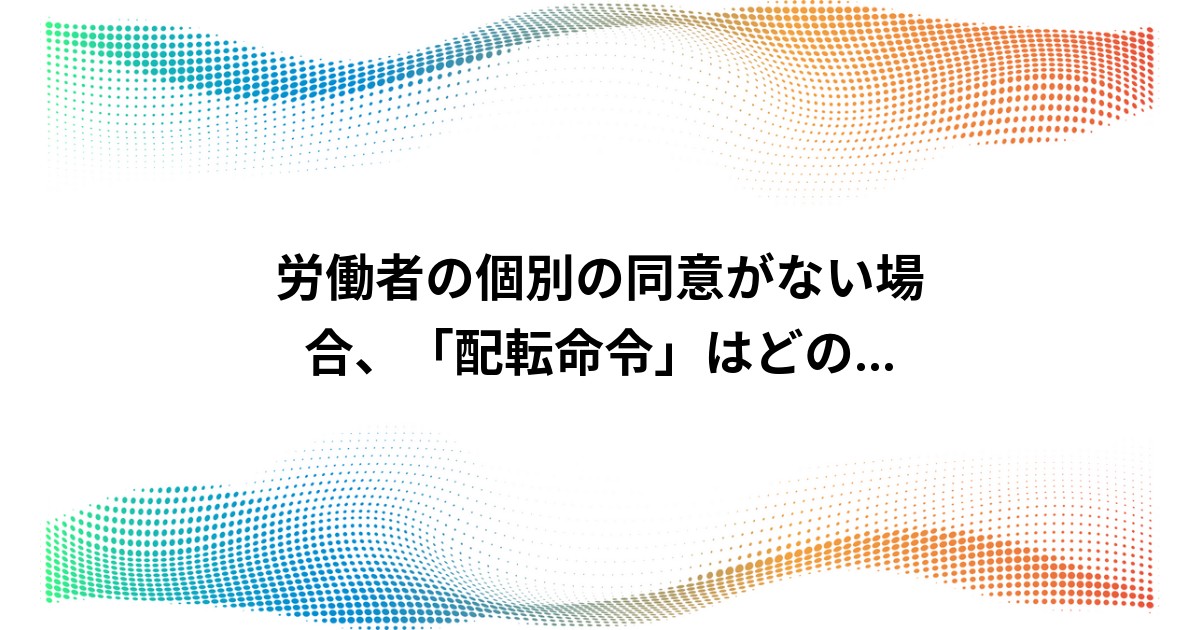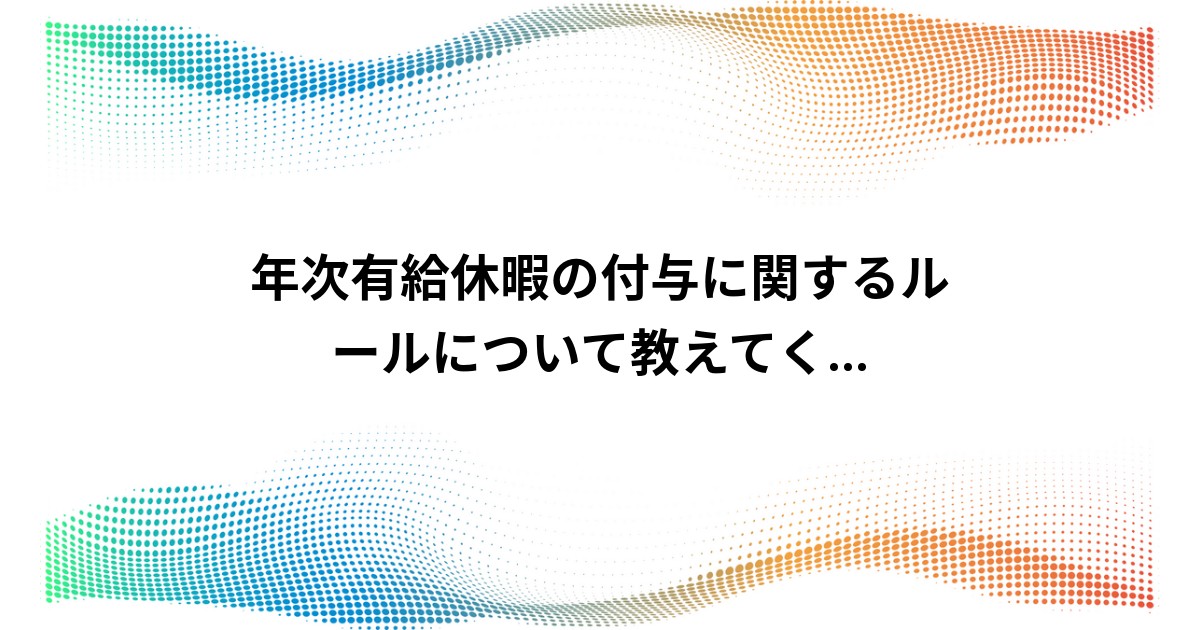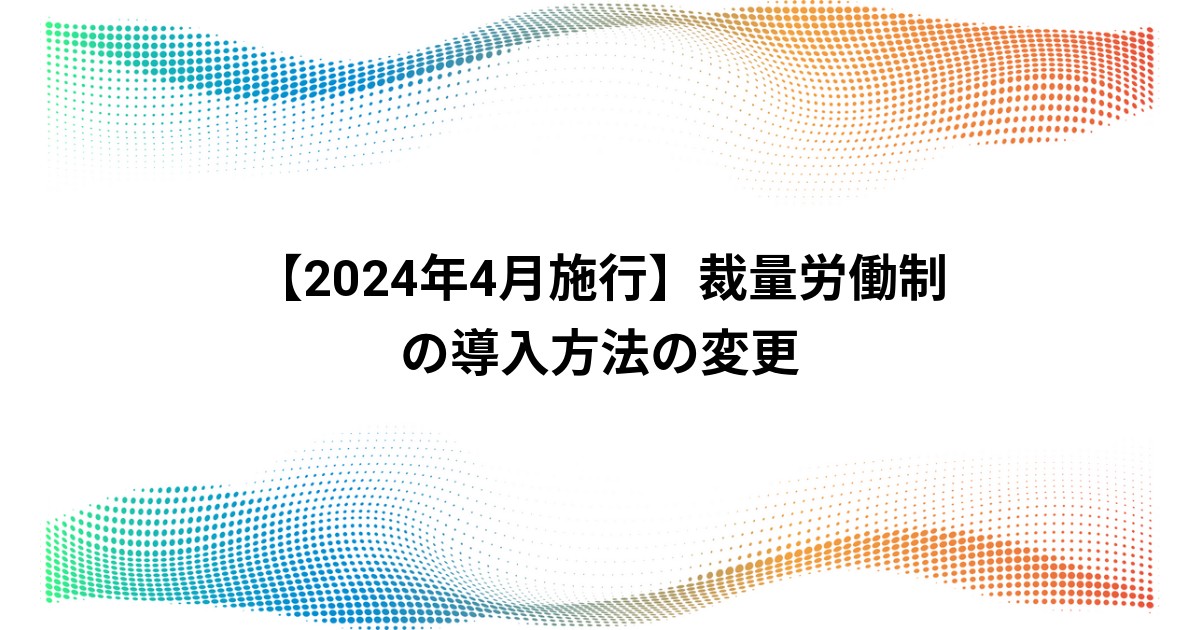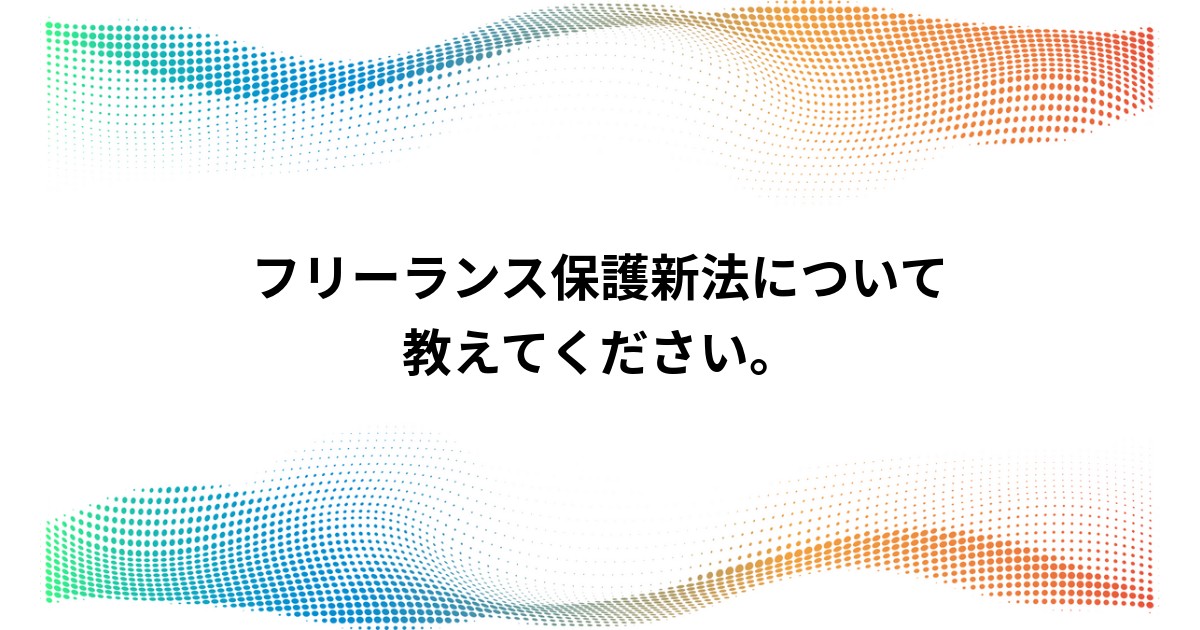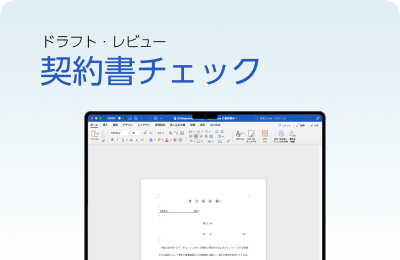目次
本記事の要約
インターンシップを活用する際には、法的なリスクを回避するためにいくつかの重要な点に注意が必要です。
まず、名称がインターンシップであっても、実際の業務内容によっては労働者とみなされ、労働基準法などの労働関係法令が適用される可能性があります。
また、有期雇用契約を結ぶ場合には、契約期間や労働条件を明示し、必要な書面を交付することが法律で義務づけられています。
さらに、無報酬であっても実質的に業務に従事していれば賃金支払義務が生じる可能性があり、最低賃金法違反などのリスクがある点にも注意が必要です。
加えて、インターン中の事故などに備えて、労災保険の適用可否や損害賠償の範囲をあらかじめ整理しておくことが望まれます。
最後に、業務情報に触れる機会がある場合には、秘密保持契約の締結や個人情報の管理体制を整えておくことも不可欠です。
以下に詳しく説明します。
1.はじめに
(1)インターンシップとは
インターンシップとは、学生が一定期間企業や官公庁、その他の団体で実務を体験する制度です。
企業は、学生に自社の業務や社風を理解してもらう機会として位置づけることが多く、採用活動の一環として活用されることもあります。
文部科学省、厚生労働省、経済産業省が公表している「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」では、インターンシップは「学生が自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義されています。
インターンシップの類型は多様化しており、数日間の短期体験型のものから、長期間にわたって業務に実際に従事する実践型のものまで存在します。
そのため、インターンシップにおける契約関係や法的リスクの把握は、企業にとって極めて重要です。
(2)インターンシップの活用事例
企業においては、インターンシップを以下のように活用する事例が多く見られます。
- 採用前の人物評価(いわゆる「お試し採用」的な活用)
- 若年層への企業認知度向上
- プロジェクト型インターンによる課題解決型業務への参加
- 特定の専門分野(IT、金融、法律等)における実践的教育
2.インターン生との契約
(1)インターン生との契約の注意点
インターンシップの対象者(インターン生)においても、インターンシップを企業の指揮命令のもとで業務を行う場合には、「労働者」に該当する可能性があります(労働基準法第9条)。
このため、契約の内容にかかわらず、実態として労働者性が認められる場合には、最低賃金や労働時間、休憩・休日などの労働関係法令が適用されることになります。
そのため、企業がインターンシップを受け入れる際には、契約形態や実態が適切であるかを慎重に確認する必要があります。
(2)有期雇用契約
ア.概要
学生と有期雇用契約を締結する場合、その契約は労働契約であり、労働基準法や労働契約法の規定が全面的に適用されます。
イ.契約期間の制限
労働契約法第17条第1項により、有期労働契約は「やむを得ない事由がある場合を除き、使用者は当該期間の中途において解雇することができない」とされており、解雇は限定的にしか認められません。
ウ.労働条件の明示
労働基準法第15条および労働契約法第4条により、労働条件の明示が義務付けられています。具体的には、労働契約の期間、就業の場所、業務内容、労働時間、賃金等について書面で明示する必要があります。
(3)業務委託契約
ア.概要
業務委託契約とは、民法上の請負契約(民法第632条)または委任契約(民法第643条)に該当する契約です。
企業とインターン生が独立した事業者として契約を締結する形態となります。
イ.労働者性の否定
たとえ契約が業務委託契約であっても、実態として企業の指揮命令のもとで働いていれば、労働者性が認められる可能性があります(労働基準法第9条)。
形式的な契約の名称よりも、実態に基づいた判断がなされます。
3.インターンシップを有期雇用とした場合の注意点
有期雇用契約に基づいてインターンシップを実施する場合、以下の点に特に注意が必要です。
- 労働条件の明示(労働基準法第15条)
- 労働時間・休憩・休日の確保(同法第32条、第34条、第35条)
- 最低賃金の遵守(最低賃金法第4条)
- 労災保険の適用(労働者災害補償保険法第3条)
また、インターンであっても就業規則の適用対象となる場合があり、インターン生に対しても就業規則の周知義務が課されます(労働基準法第106条)。
さらに、学生に業務の一部を担わせる場合には、指導監督体制の整備も不可欠です。
誤って違法な長時間労働や安全配慮義務違反が生じれば、企業の責任が問われることになります。
4.インターンシップを業務委託とした場合の注意点
業務委託契約を締結してインターンシップを受け入れる場合でも、以下のようなリスクが存在します。
ア.労働者性の判断リスク
先述のとおり、契約書で「業務委託」と明記していたとしても、実態として企業の指揮命令下で働かせていれば、労働者性が否定されるとは限りません。
このため、契約の実行段階においても、業務内容の独立性、時間拘束の有無、報酬の性質などを慎重に管理する必要があります。
イ.安全配慮義務の問題
業務委託契約であっても、インターン生が企業内で作業を行う以上、一定の安全配慮義務を負うことがあります。
特に、未成年者や実務未経験の学生を受け入れる場合には、教育・監督体制の構築が求められます。
ウ.報酬の支払と税務処理
報酬を支払う場合には、給与ではなく報酬・料金として源泉徴収の対象となる可能性があります(所得税法第204条)。
そのため、契約時には支払条件や税務上の取り扱いについても確認しておくべきです。
おわりに
インターンシップは、企業にとって優秀な人材との接点を持つ貴重な機会であり、事業成長の一助となる制度です。
しかし、その受入れにあたっては、契約形態や実態に応じた法的リスクを正確に把握し、適切に対応することが重要です。