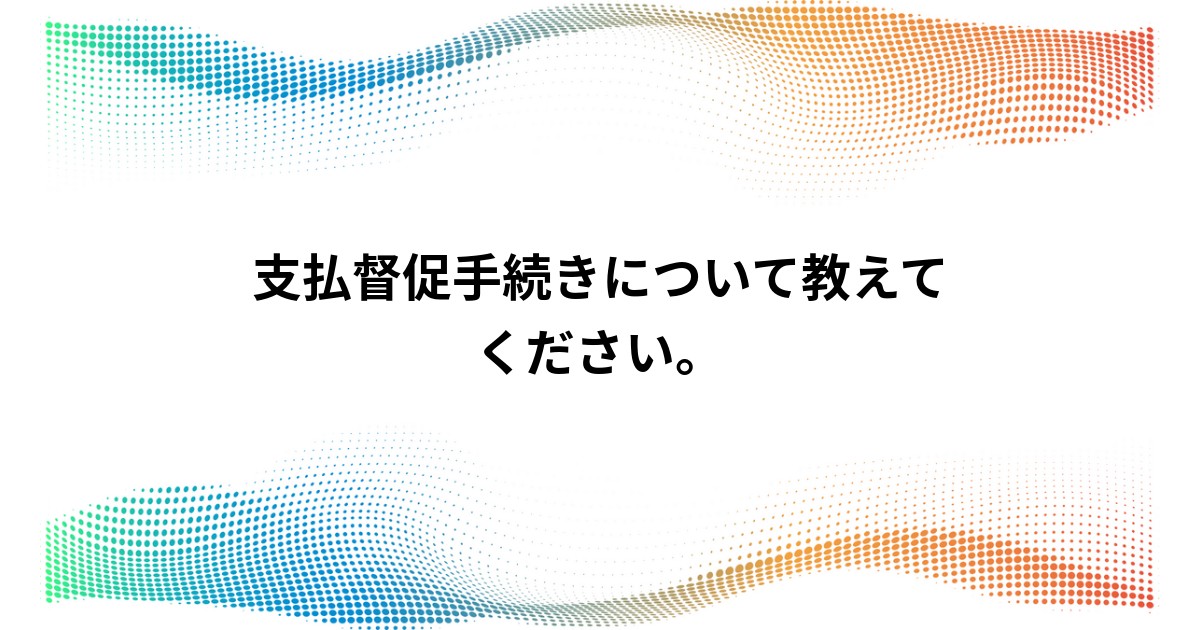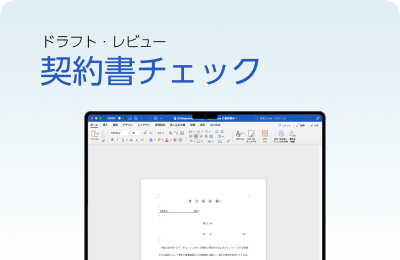目次
第1 はじめに
取引先からの入金が遅れている、貸したお金が返ってこないなど、債権回収は避けて通れない問題です。
そのような場合に、比較的簡易迅速に債務名義を取得できる法的手続きとして「支払督促」があります。
本記事では、支払督促手続きの概要から具体的な手続の流れ、メリット・デメリットを条文や実務上のポイントを交えながら分かりやすく解説します。
第2 支払督促の概要
支払督促とは、裁判所書記官が債務者に対して支払を命じる略式の手続です(民事訴訟法第382条)。
通常の訴訟とは異なり、裁判所での審理(口頭弁論)を経ずに、書類審査のみで手続が進むため、迅速な解決が期待できる点が特徴です。
債権者は、この手続きにより、強制執行(差押えなど)を行うために必要な公的な文書である「債務名義」の取得をすることを目指すことができます。
支払督促は、請求内容について当事者間に争いがないような場合に有効な手段となります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html
第3 支払督促が適する事案
支払督促は、主に以下のようなケースでの活用が考えられます。
(1)請求権の存在や金額について、相手方が争わない可能性が高い事案
具体的には、売掛金、貸金、請負代金、立替金、賃料、求償金など、契約書や請求書、納品書といった客観的な証拠があり、債務の存在や金額について相手方が明確に争ってくる可能性が低い場合です。
後述のように、相手方が異議を申し立てると、結局は通常訴訟に移行してしまうため、この点が最も重要なポイントとなります。
(2)相手方(債務者)の住所(送達先)が判明している事案
支払督促は、裁判所書記官が発する支払督促正本を債務者に送達する必要があります(民事訴訟法第388条第1項)。
そのため、債務者の正確な住所・居所が判明しており、送達が可能であることが前提となります。
相手方の住所が不明な場合や、海外に居住している場合には利用できません。
(3)迅速に債務名義を取得したい事案
相手方から異議が出なければ、通常の訴訟に比べて格段に短い期間で債務名義を取得できます。
(4)支払いを促したい事案
裁判所という公的機関から正式な書類(支払督促)が送達されるため、債務者に対して心理的なプレッシャーを与え、自主的な支払を促す効果が期待できます。
(5)デメリットが受け入れられる
支払督促にデメリットもありますので、「第4 デメリット」に該当してしまう事案ではないかもご確認ください。
第4 デメリット
非常に便利に見える支払督促ですが、支払督促には以下のようなデメリットや注意点も存在します。
(1)異議による通常訴訟への移行
債務者から督促異議が申し立てられると、手続は自動的に通常訴訟へ移行します(民事訴訟法第395条)。
この場合、支払督促に要した時間や労力が結果的に遠回りになる可能性があります。
最初から訴訟提起した方が早かったというケースも十分にあり得ます。
(2)通常訴訟への移行がされた場合の管轄
通常訴訟に移行された場合、その管轄は債務者の住所地になる可能性があります。
このため、遠方に出向かなければならない場合があり得ます。
金銭請求の場合、通常訴訟を提起する場合には、債権者の住所地で行うことができることが多いといえますが、支払督促に異議がされてしまうとそのようにならないことがあります。
(3)相手方の住所等が不明な場合は利用不可
支払督促は債務者への送達が前提となるため、相手方の住所等が不明な場合や、送達ができない場合には利用できません。
公示送達(裁判所の掲示板に掲示することで送達があったとみなす制度)も認められていません。
(4)請求内容に争いがある事案には不向き
債務の存在や金額について相手方が争ってくることが予想される場合には、督促異議が出される可能性が高いため、支払督促は適していません。
このような場合は、初めから通常訴訟を検討すべきでしょう。
(5)債務者に資力がない場合は実効性が低い
これは支払督促に限ったことではありませんが、いくら債務名義を取得しても、債務者に差押えできる財産がなければ、現実の回収は困難です。
(6)外国送達ができない
支払督促は、外国においてすべき送達については、その効力を有しません(民事訴訟法第394条)。
債務者が海外にいる場合は利用できません。
第5 支払督促手続きの流れ
1 申立てから送達まで
(1)支払督促の申立て
債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に、申立書により、申し立てをします。
必須ではありませんが、契約書等の写しを添付することが一般的です。
(2)裁判所書記官による審査・支払督促の発付
裁判所書記官が申立書を審査し、適法であれば支払督促を発します。
(3)支払督促の送達
債務者に支払督促が送達される必要があります。
2 債務者の対応と債権者の次のステップ
支払督促送達後の債務者の対応は以下の通りです。
(1)債務者が2週間以内に「督促異議」を申し立てない場合
ア 債権者は、上記2週間の経過後30日以内に仮執行宣言を申し立てます。
イ この申立てが適法なら、裁判所書記官は仮執行宣言を付した支払督促を双方に送達します。
ウ 債務者は、さらに送達から2週間以内に督促異議を申し立てられます。
エ 支払督促の確定:上記異議がなければ、支払督促は確定判決と同一の効力を持ちます。
(2)債務者が「異議」を申し立てた場合
ア 支払督促はその範囲で効力を失い、自動的に通常訴訟へ移行します。
イ 支払督促申立時に訴えの提起があったとみなされ、管轄の簡易裁判所または地方裁判所で審理されます。