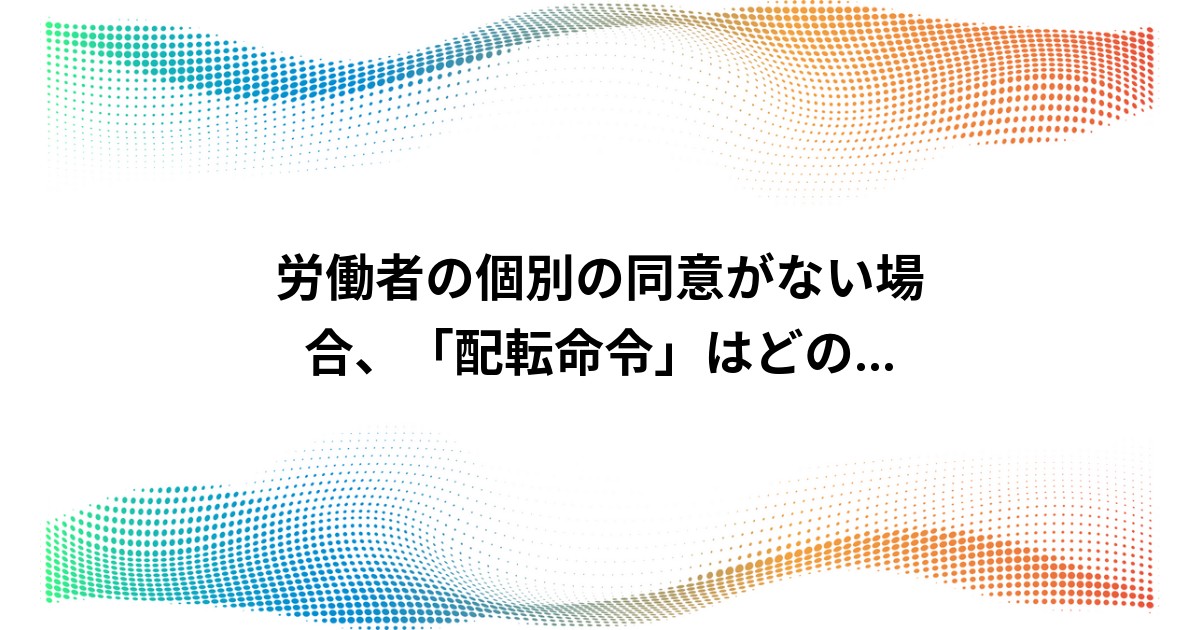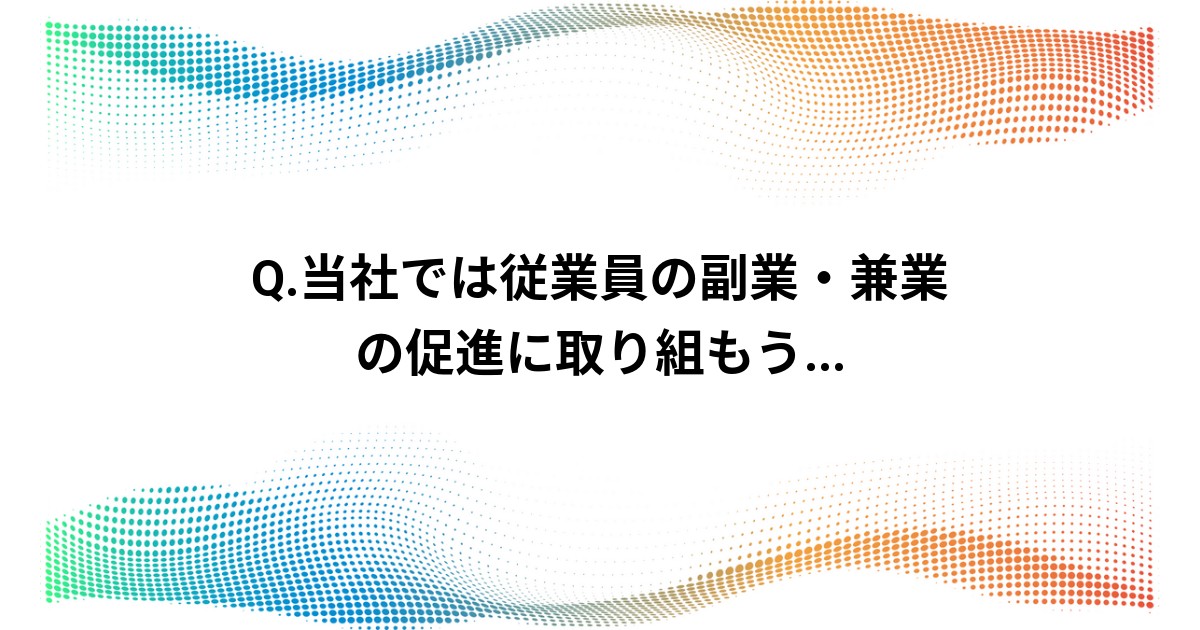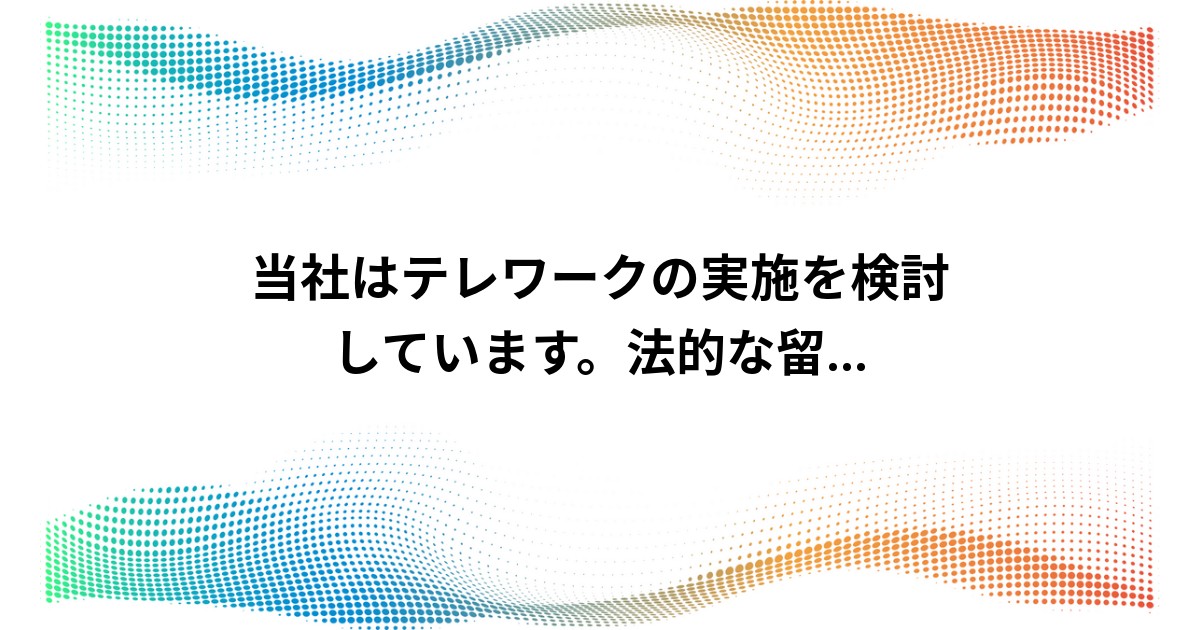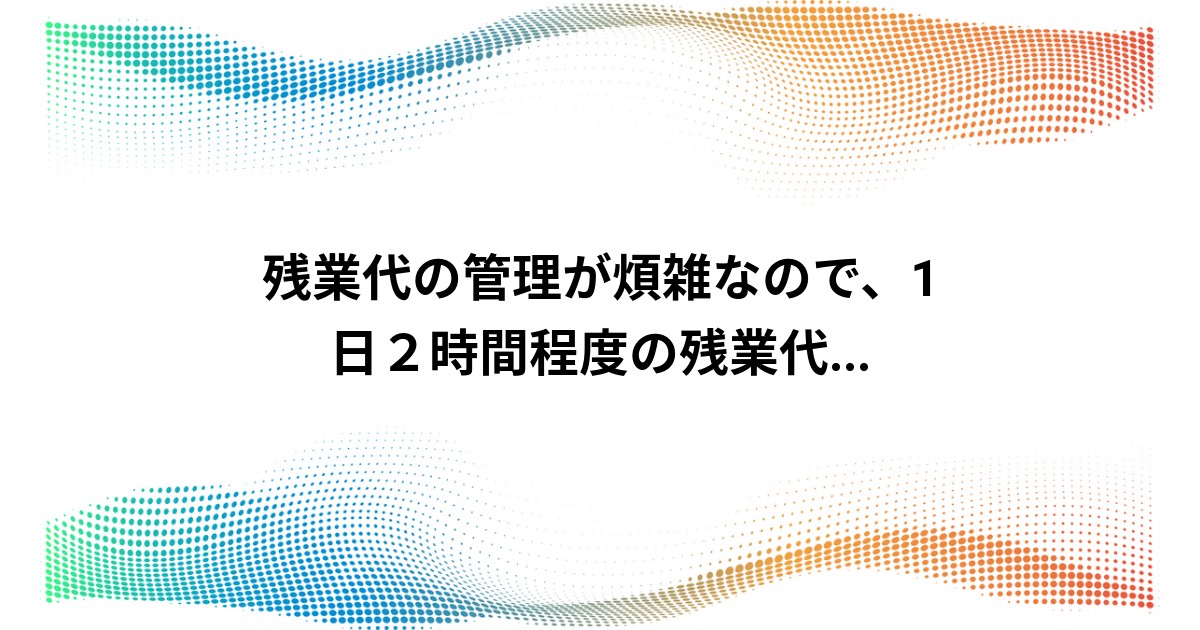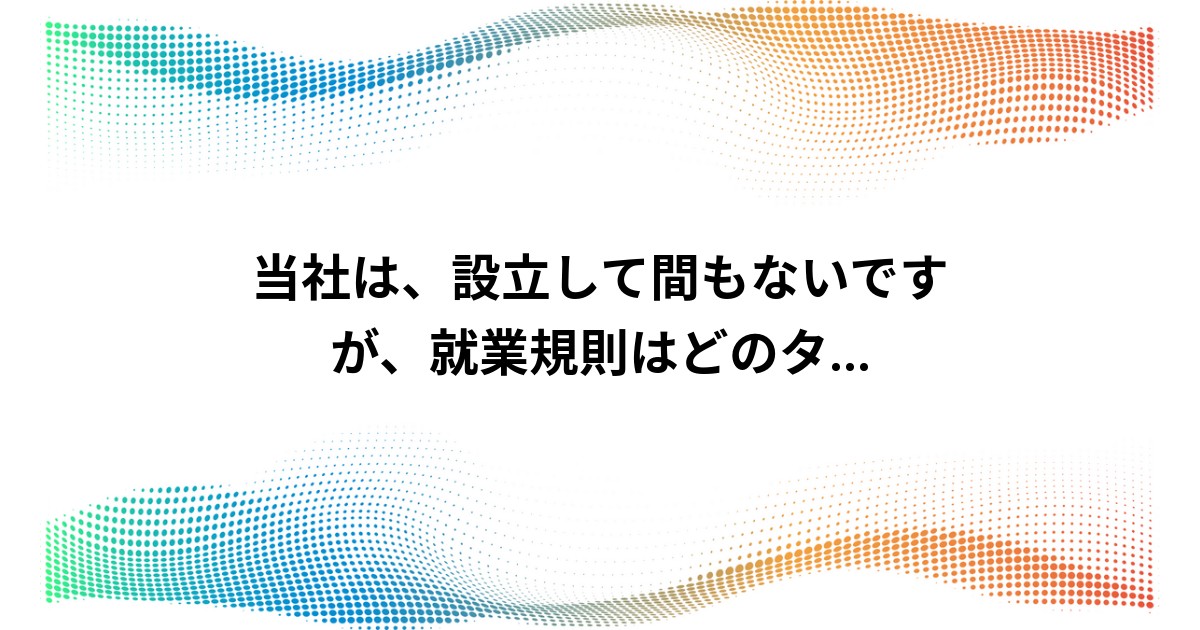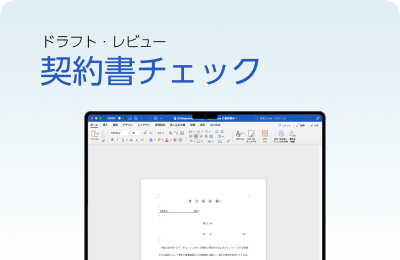配転命令は、それが労働契約の内容になっていると評価できることを前提として、業務上の必要性・合理性があり、かつ、労働者に著しい不利益を与えない場合に認められます。
設問が前提としているとおり、就業規則や労働契約に定めがなくても使用者と労働者は配転について合意することができます。以下では、そのような個別合意がない場合について説明します。
- はじめに
「配転命令」は、労働基準法等で定義づけられているものではありませんが、企業が特定の労働者に対して、長期間にわたって異なる地理的な場所や部署への移動を命じる法的な措置です。
勤務地の変更を「転勤」、所属部署の変更を「配転」ないし「配置転換」といいます。
配転命令は、本来は組織の運営効率を高めるためや、労働者のスキルをより適切な場所で活用するために行われますが、近年では企業の安全配慮義務に基づいてハラスメントの当事者の距離を離すため行われることもあります。
なお、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務がありますが、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」は明示義務の対象となっています(労基法第15条、同施行規則第5条一の三・2024年4月施行)。このため、配転命令の可能性がある場合には、採用時に交付する労働条件通知書にそれを記載するべきです。
- 「配転命令」が労働契約の内容になっていると評価できること
「配転命令」は労使間の労働契約の内容を変更することになります。
一旦締結された契約は、契約の一方当事者が相手方の同意なく契約内容を変更することはできません。例えば、大家さんはアパートの家賃を勝手に値上げすることはできません。
同様に、労働契約においても契約内容を変更するためには契約の相手方(労働者)の同意が必要となります。
ただ、労働契約は、売買契約のような他の典型契約と比べて、長期間の継続的な契約であるため労働契約締結時に将来の当事者の権利義務を全て定められないこと、労働者は企業の事業目的を達成するために他の労働者と集団で組織的に役務提供すること性質的な違いがあるため、契約についても独特の構成となっています。
具体的には、その企業の労働者全般に適用される「就業規則」と、企業と労働者が締結する個別の「労働契約書」が契約内容を定義する書面になります。就業規則が定める基準より低い条件を個別の労働契約で定めた場合は就業規則が優先することになります(労働契約法12条)。
このため、企業が配転命令をすることができるようにしておくためには、就業規則に、以下のようなルールを設定しておくべきです。
- 会社は、労働者に対して、業務上の必要性があるときは、出向、転勤、担当職種及び就業場所の変更を命じることができる。
就業規則に配転命令に関するルールがあったとしても、労働契約において、勤務地や職種を限定する合意があったと認められるときは、配転命令が契約違反として無効となるケースがあります。
例えば、採用面接において、就職を希望する労働者側から家庭の事情によって勤務地の異動や職種の変更には対応できないと申し入れがあり、企業側がそれを受け入れて採用した場合には、労働契約の内容として勤務地や職種を限定する合意があったことになります。
また、労働者が担当してきた業務が、国家資格や特殊技能に基づいて行われるようなものである場合には、黙示的に職種を限定する合意があったと認められることがあります。
- 業務上の必要性・合理性があること
「配転命令」のルールが就業規則などに記載されていたとしても、「配転命令」は労働者の不利益を伴う場合があるため、合理的な範囲で行われなければ権限濫用であると評価されることがあります。
最高裁(昭61.7.14)は、
・転勤命令について業務上の必要性が存しない場合
・業務上の必要性が存する場合であっても、転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき
・ 労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき
は、特段の事情が存する場合でない限り転勤命令は権利濫用となると判断しています。
ここにいう「業務上の必要性」は、一般的な企業の人事政策としての、業務効率化、人員の適正配置、教育、モチベーション向上や事業改革への対応など特に高度なものである必要はありません。
他方で、配転命令の目的が退職を強いるためである場合、労働者にとって経済的に著しい不利益が生じる場合、労働者の資格に基づく担当職務への期待を不当に裏切る場合(運行管理者を倉庫業務へ、フライトアテンダントを地上勤務へ、薬学部教授を薬剤師へ)などは合理性が否定されています。
- 労働者に著しい不利益を与えないこと
上述の最高裁判例が「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」は、配転命令が権限濫用になると示すとおり、労働者にとって著しい経済的不利益がある場合や、家族の介護に著しい支障が生じるなど円満な家庭生活を困難にするような場合には配転命令は認められません。
このうち、労働者にとって著しい経済的不利益がある場合に関しては、経済的な不利益を緩和するための一時手当や引越代などを併せて支給することによって合理性が補完されることがあります。
- 配転命令手続の進め方
配転命令は、業務上の必要性が背景となるため、事前に、社内人事の状況、課題、対策などについてとりまとめる必要があります。
次に、配転の根拠となる就業規則及び労働契約の内容を確認するとともに、配転を行った場合に対象となる労働者の待遇にどのような変更が生じるかを把握します。
そして、対象となる労働者のキャリアや個人的な事情を把握するために面談を行い、配転について提案し、理解を得ます。
そのうえで、特定の日付で配転命令を行います。
紛争を未然に防ぐために、配転を行う前には、労働者との十分な対話と協議を行い、労働者の不安や疑問を解消し、双方の理解を深めるべきです。
なお、ハラスメントの当事者の接触機会を減らすために配転を行う場合、被害者側を配転させると通報に対する不利益処分を行ったものとして違法とされる可能性があります。この点にも注意が必要です。
最後に、配転命令に伴って職務等級の下方変更(降格)、それに伴って給与の減額が生じる場合があります。これについても、基本的には、上述の枠組みに沿って考えることになります。つまり、労働契約の内容が、そのようなケースを予定していることを前提として、合理的な目的で、相当の範囲で行われたものか否かが問題となります。
企業側としては、給与の原資となる財務状況が一定であるとすれば、柔軟に減給と昇給を行って労働者のモチベーションを向上させたい。しかし、労働者側からすれば、減給は生活に直結する不利益である。そこで、紛争回避のためには慎重にコミュニュケーションを行って労働者の理解を得る対応が求められます。
以上