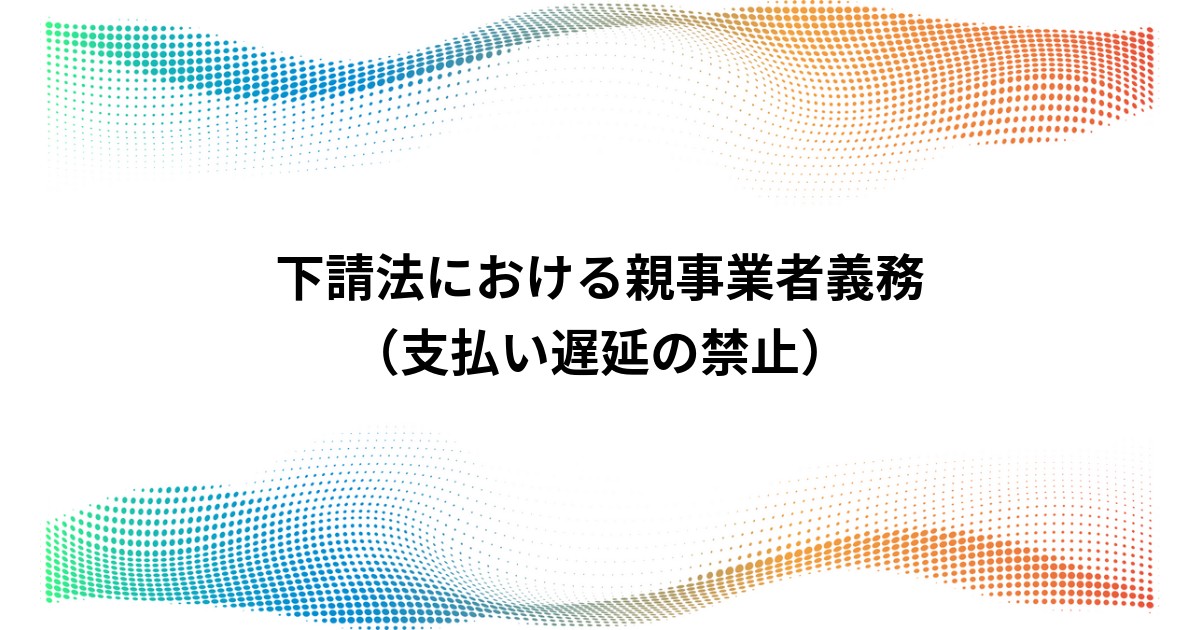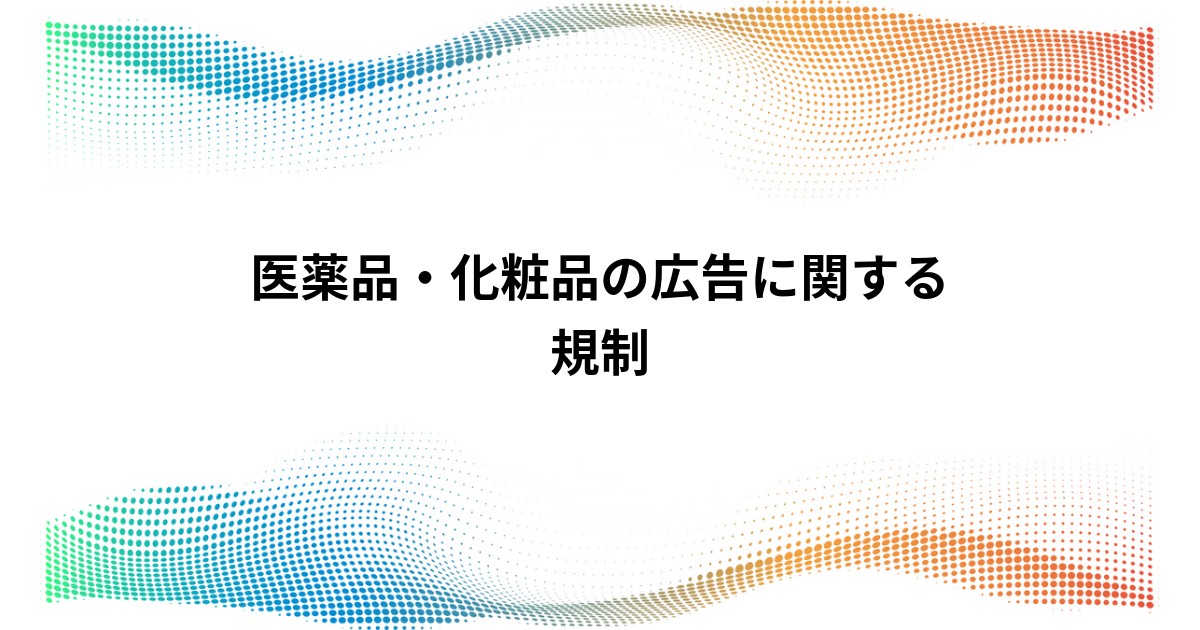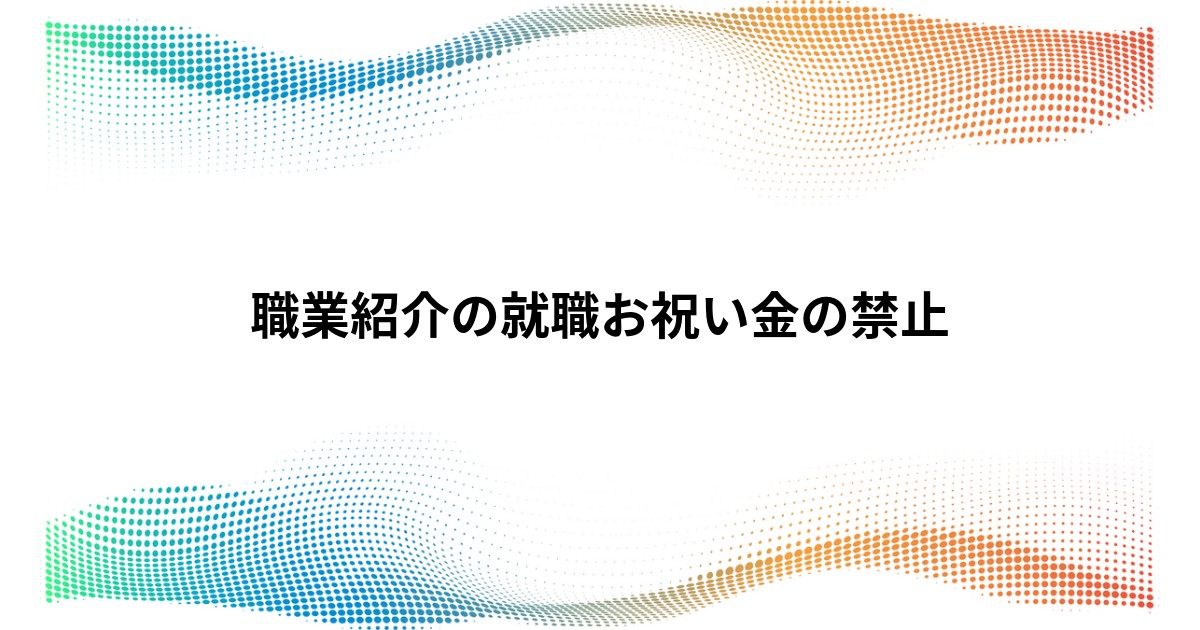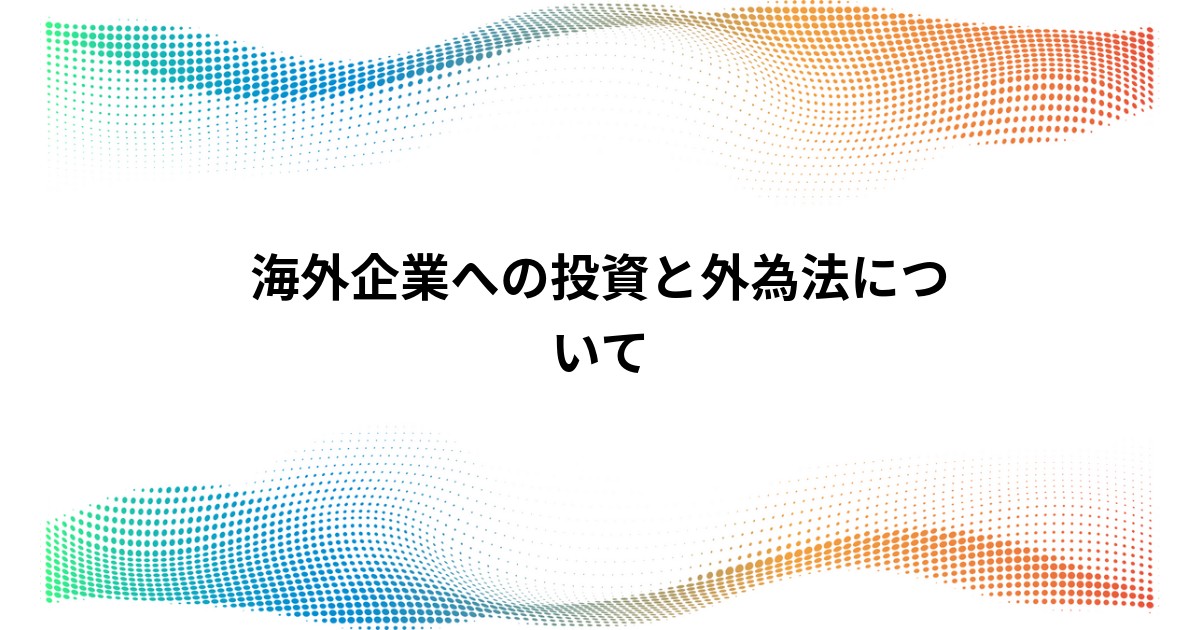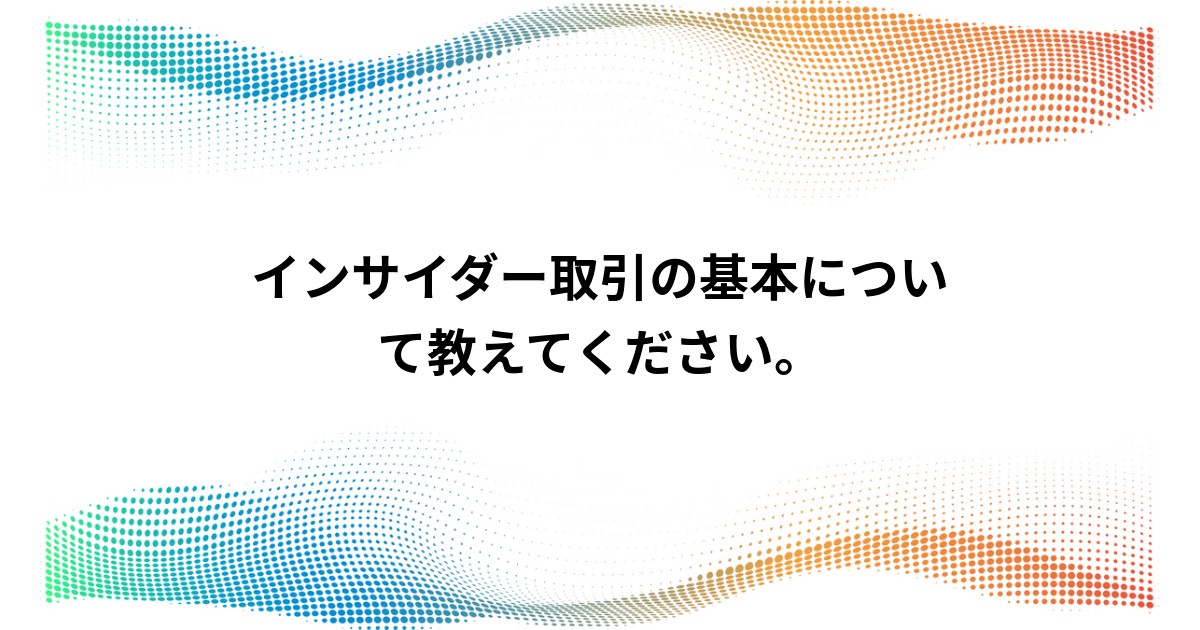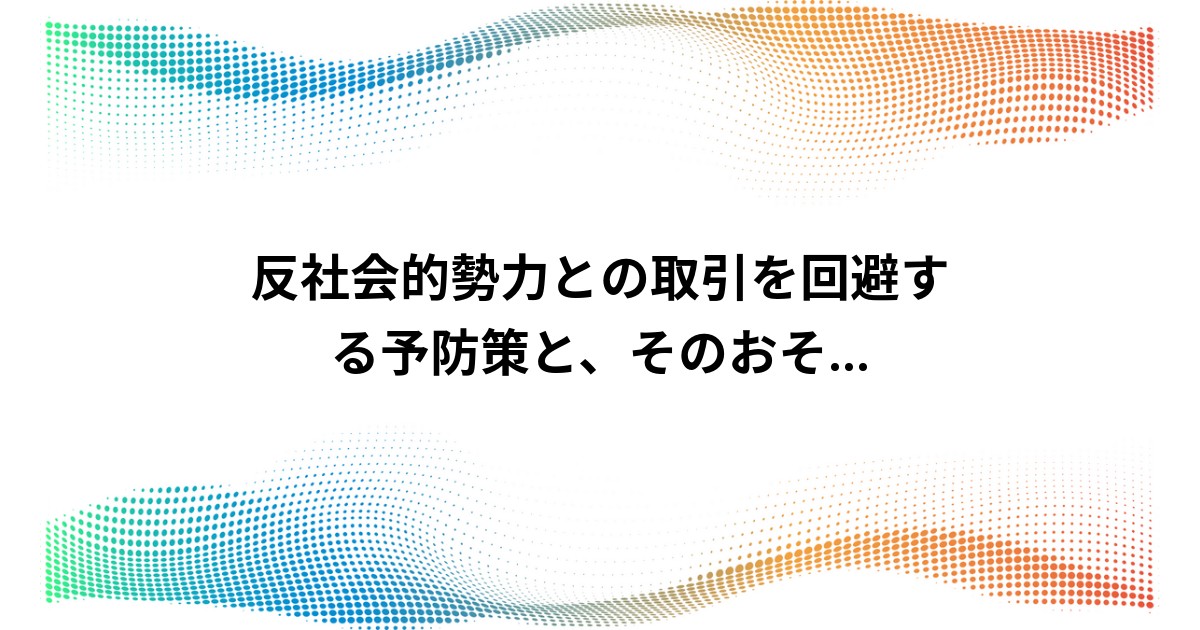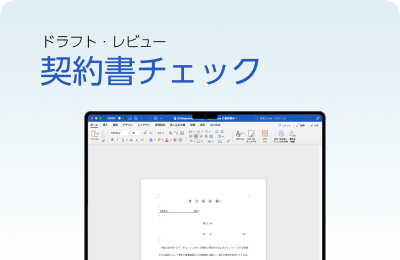第1 はじめに
下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者に契約書類の作成・交付、下請代金の減額や、買いたたき、不当な返品や受領拒否などを定めています。
本稿では、特に下請代金の支払期限のルールについて解説します。
本記事では原則的なルールとともに、60日を超えた支払いが許容されるのではないかと誤解されやすい点について解説しています。
第2 下請法における支払遅延の禁止(原則)
1 支払期日を設定する義務
親事業者には、下請事業者の給付(納品や役務提供)を受領した日から起算して60日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払期日を定める義務があります(下請法第2条の2第1項)。
単に60日以内に設定すればよいわけではなく、不当に長い支払期日は認められません。
【親事業者の義務】
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyagimu.html
2 支払遅延となる3つのケース
具体的に「支払遅延」と判断されるのは、主に以下の3つのパターンです。
(1)支払期日が受領日から60日以内に定められている場合
その定められた支払期日までに支払わなければ支払遅延となります。
(2)支払期日が受領日から60日を超えて定められている場合
支払期日の設定自体が違法であるので、受領日から60日目が支払期日とみなされ、その日までに支払わなければ支払遅延となります。
(3)支払期日が定められていない場合
給付を受領した日そのものが支払期日となり、その日のうちに支払わなければ支払遅延となります。
3 支払遅延のペナルティ
親事業者が支払遅延を起こした場合、下請事業者に対し、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます(下請法第4条の2)。
第3 支払期日の「起算日」となる受領日
60日のカウントを開始する「起算日」の考え方は、委託内容によって異なります。
1 委託内容ごとの起算日
(1)製造委託・修理委託 下請事業者が納品した物品を、親事業者が検査の有無にかかわらず受け取り、自己の占有下に置いた日が「受領日」です。
(2)情報成果物作成委託(ソフトウェア制作など) 成果物を記録した媒体を受け取った日、または電子メールでの受信などにより、その情報成果物を親事業者が自己の支配下に置いた日が「受領日」です。
(3)役務提供委託(運送、保守など) 「受領」という概念はなく、下請事業者が委託された役務の提供を完了した日が起算日となります。
2 実務上の論点:月単位の締切制度
「毎月末日締め、翌月末日払い」といった締切制度では、月の暦によっては支払日が受領日から60日を超えてしまうことがあります。
この場合でも、親事業者としては可能な限り60日を超えないよう配慮することが望ましいといえます。
ただし、公正取引委員会などの運用では「受領後2か月以内」として弾力的に扱われ、数日の超過であれば直ちに問題とはされないところです。
第4 支払い時期の変更が許容される場合
実務では「下請事業者側に原因があるのだから支払いが遅れても仕方ない」と考えたくなる場面があるかもしれません。
しかし、下請法では、親事業者の支払遅延が正当化されるケースは極めて限定的です。
1 許容されないケース
以下のようなケースでは、たとえ下請事業者側に起因する事情があっても、支払遅延は正当化されません。
(1)下請事業者からの請求書発行が遅れた場合
親事業者は、請求書の有無にかかわらず、定められた支払期日までに支払う義務があります。
社内手続き上、請求書が必要な場合は、下請事業者に提出を促すなど、支払遅延とならないよう管理する責任が親事業者にあり、支払い遅延と評価されることが通常です。
(2)契約で求められる報告がなかった場合
支払期日の起算日は、あくまで「役務を提供した日」です。
報告書の提出が遅れたことを理由に支払いを遅らせることは、通常、支払遅延に該当します。
(3)下請事業者との合意があった場合
たとえ下請事業者から依頼があったり、双方の合意があったりしても、受領日から60日を超えて支払うことは下請法違反となります。
下請法は、強行法規であり、当事者間の合意によって適用を免れることはできません。
2 例外的に、当初の起算日から60日を超えるケース
支払遅延が問題とならない、あるいは起算日の考え方が変わる例外的なケースも存在します。
(1)給付内容に瑕疵があり「やり直し」をさせた場合
下請事業者の納品物に瑕疵があるなど、下請事業者の責任により、受領後60日以内にやり直しをさせた場合は、やり直し後の物品を改めて受領した日が新たな支払期日の起算日となります。
(2)金融機関の休業日にあたる場合
支払期日が金融機関の休業日にあたる場合、以下の2つの要件を満たせば、結果として受領日から60日を超えても問題ないとされています。
ア 順延する期間が2日以内であること。
イ 親事業者と下請事業者との間で、支払日を金融機関の翌営業日に順延することが、あらかじめ書面で合意されていること。
(3)下請代金の額が未確定な場合(修理委託など)
修理委託などで当初代金額を確定できない場合でも、親事業者は修理内容を確認し、標準料金表を参考にするなど、合理的に算定可能な金額を可能な限り調査し、支払うべきとされています。