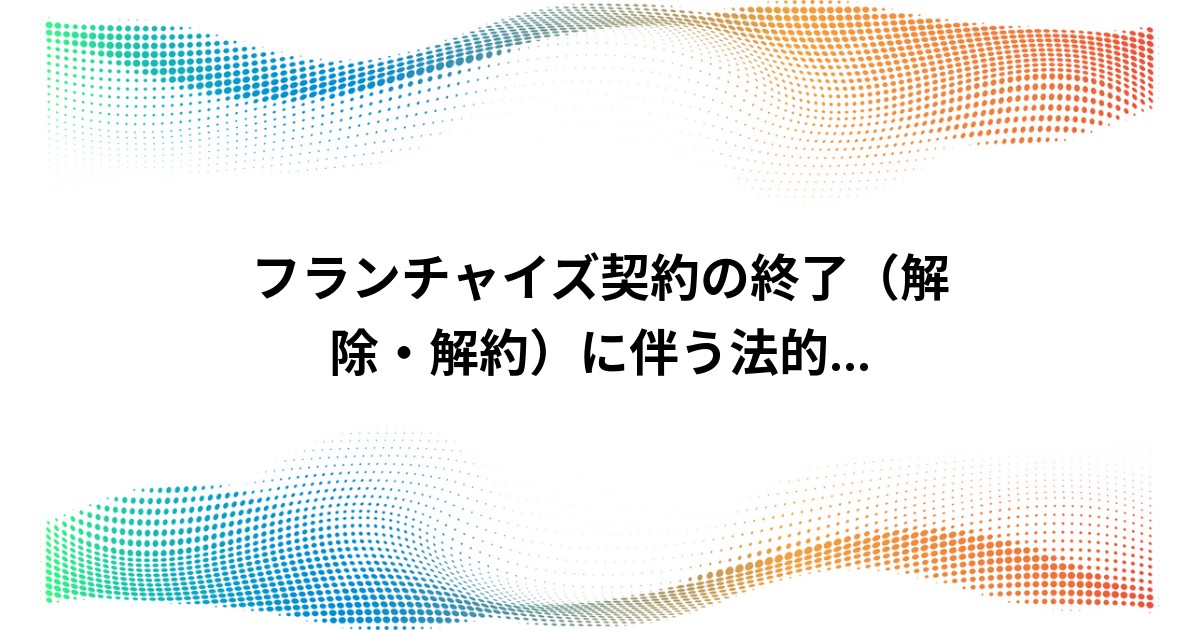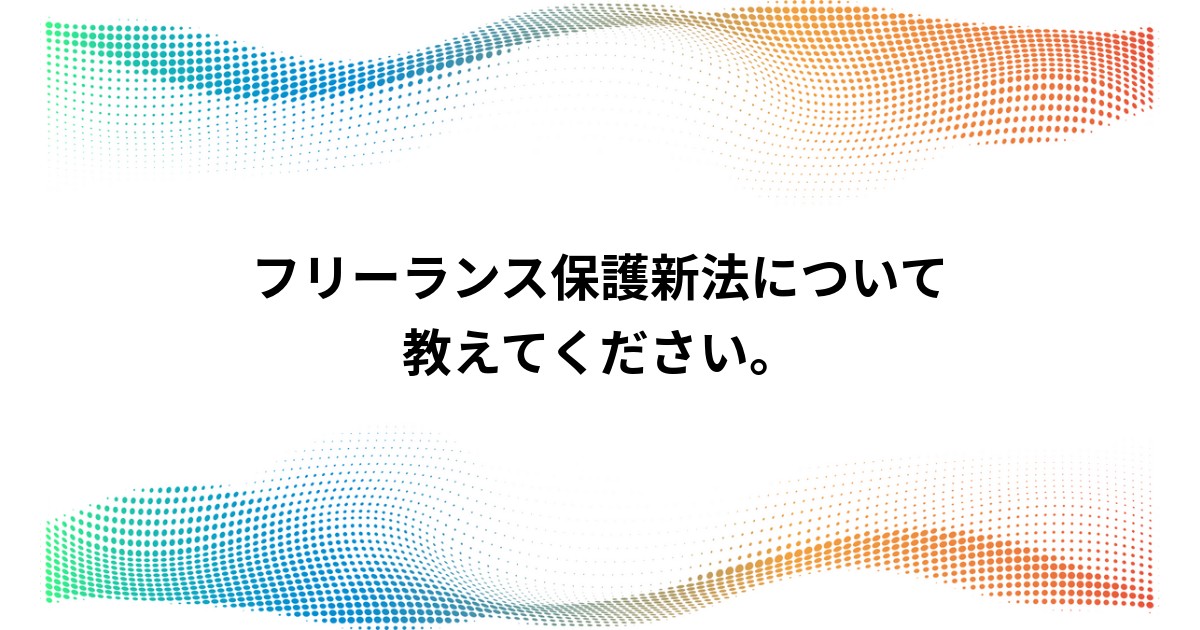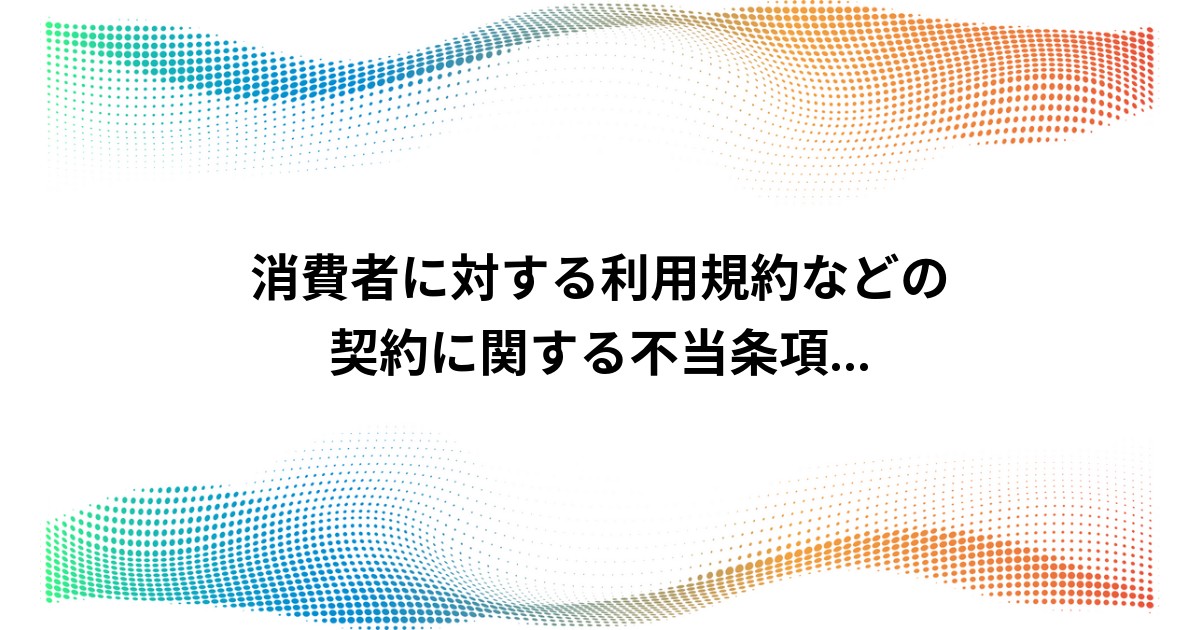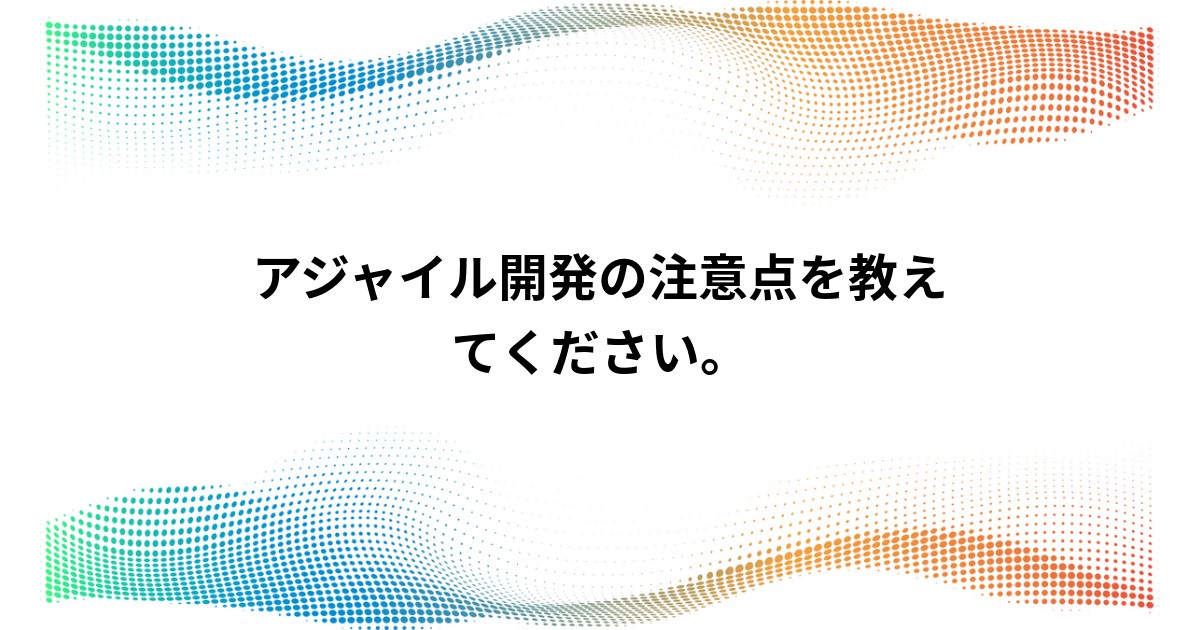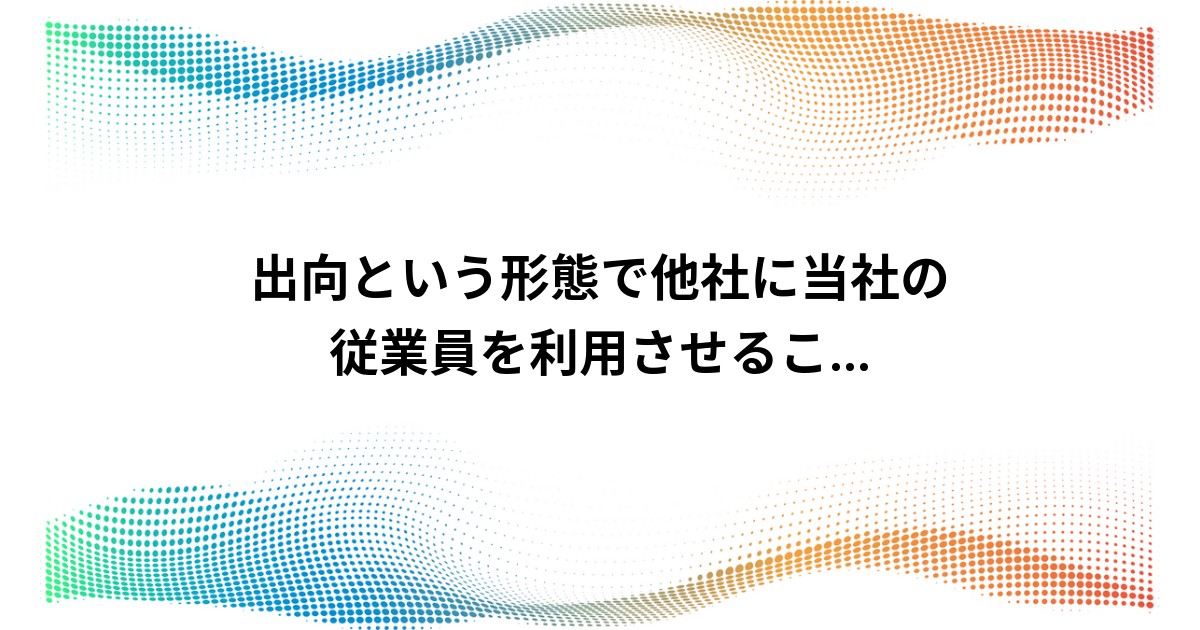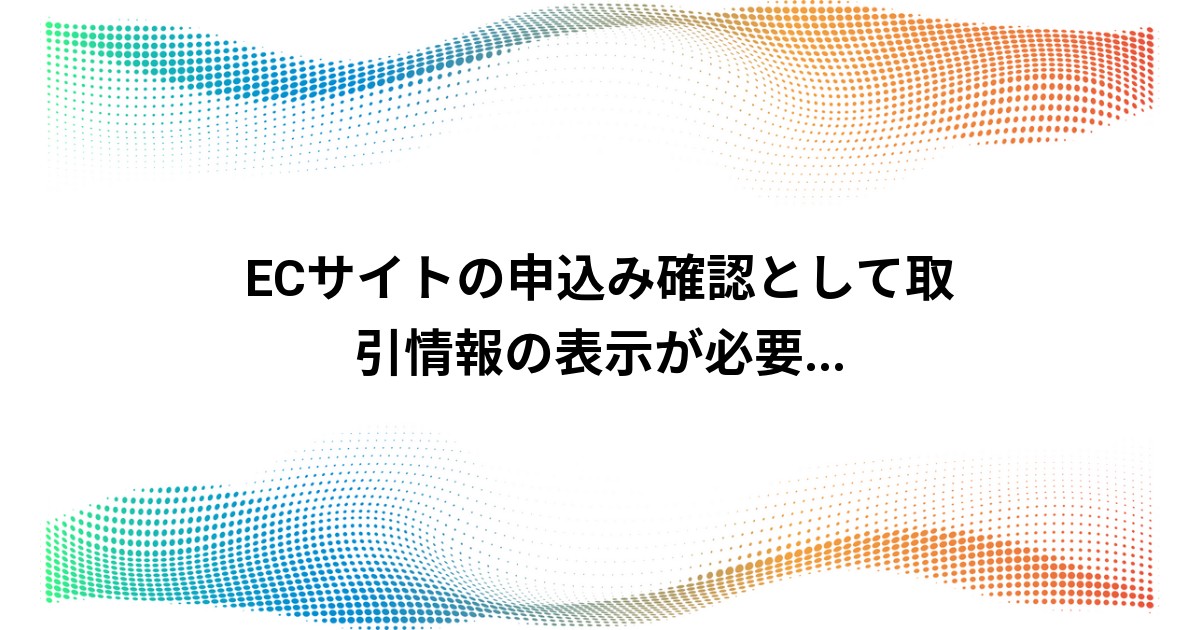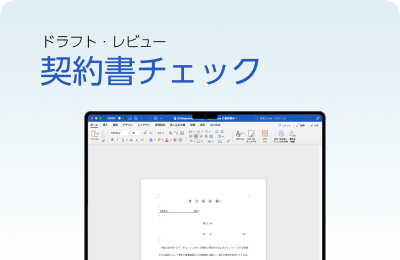1 はじめに
契約書では損害賠償条項が設けられ、損害を生じさせた当事者が賠償するべき損害の範囲が定められることがあります。
このような損害賠償責任の範囲を定める条項は、当事者の利害関係が対立するため、契約交渉の主要な問題点となることが多いといえます。
例えば、損害賠償に関する条項の契約交渉において、「特別損害に限る」や「損害額は○○万円を上限とする」「直接かつ現実に生じた損害に限る」「逸失利益を除く」などといった文言を追記するのか否かが問題視されることがあります。
本記事では、このような契約交渉における考え方を理解していただけるように損害の範囲に関する基本を解説します。
2 民事法に基づく基本的な考え方
民事法上は、損害賠償の範囲については、以下のように定められています。
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
第1項では、通常損害について、当然に損害賠償の範囲になることが定められています。通常損害については、債務者が予見すべきかどうかにかかわらず、債務の不履行によって損害が発生したことさえ主張・立証すれば損害賠償の範囲として認められることになります。
第2項では、特別損害について、特別の事情を予見すべきときは損害賠償の範囲になることが定められています。特別損害については、損害が発生したことを主張・立証するだけでは不十分であり、特別の事情を予見したことをも主張・立証しなければならないといえます。
民法416条の「損害」は、一般に、債務の不履行がなければあったはずの利益状態と、債務の不履行がされた実際の利益状態との差額と理解されています(差額説)。
このような「損害」の全てが賠償の範囲になると、損害の範囲は無限に広がってしまいます。
そこで、民法416条では、このような「損害」の全てが賠償の範囲になるのではなく、相当因果関係がある範囲に制限しています。
上記を踏まえると、通常損害とは何か、特別損害とは何か、という区別が重要といえます。
※なお、契約書で「委託者は、相当因果関係がある範囲に限り、損害賠償請求をすることができる」などと規定されている例があります。
これは、「限り」などと規定されているので、損害賠償の範囲を制限しているようにも見えますが、実際には、上記の民法416条と同じことを説明しているに過ぎないので、民法の原則のとおりであることを定めているに過ぎず、損害賠償の範囲を制限した規定ではないといえます。
3 通常損害・特別損害
(1)通常損害
通常損害とは、債務の不履行によって、社会通念上、通常に発生する損害をいいます。
社会通念によって判断されるため、契約上の債務不履行であれば、その契約類型や、当事者間の認識、当事者の属性、取引の内容や方法等を総合的に考慮して通常損害といえるかどうかが決まります。
例えば、個人情報の取り扱い業務を受託した受託者が、業務委託契約に違反して個人情報を漏洩した場合を想定してみると、以下のような損害は、社会通念上、通常に発生するといえるため、通常損害に分類されるといえるでしょう。
・漏洩の対策コスト(広報費用・回収費用・個人情報の本人への損害賠償の支出・対策専門家への費用支出・対策チームの人件費等)
・個人情報の漏洩によって委託者が営業を停止したときや、取引を失ったときは、その逸失利益
・個人情報の漏洩によって委託者のレピュテーションの低下が金銭評価できる場合には、その低下した部分
(2)特別損害
特別損害とは、通常損害には含まれないものであって、「特別の事情」によって生じたといえる損害をいいます。
例えば、消費者に向けて小売店が商品を販売しようとしたが、小売店の債務不履行により、その商品の引渡しができなった場合、社会通念上、消費者は商品を転売するために購入するものではないため、消費者がその商品を転売できなかった転売利益は通常損害に含まれない、と評価されるでしょう。
この場合、消費者が転売できなかったとしても、得られるはずであった転売利益は通常損害に含まれません。
しかし、仮に、消費者が転売目的で購入しており、実際に転売ができなくなった場合には、その消費者は、転売利益を受けられなくなっています。
この場合、「消費者が転売目的で購入しており、実際に転売ができなくなった」という「特別の事情」によって消費者に転売利益が得られなくなったといえるので、特別損害であるといえます。
このような特別損害については、債務者(この場合、小売店)が、「消費者が転売目的で購入しており、実際に転売ができなくなった」という「特別の事情」を「予見すべき」場合には、損害賠償の範囲に含まれることになります。
(3)契約上の留意点
上記のように、通常損害・特別損害は、契約類型や、当事者間の認識、当事者の属性、取引の内容や方法等によって区別されます。
また、特別損害については、「予見すべき」であったかどうかによって、損害賠償の範囲に含まれるかどうかが決まります。
このため、双方が損害の範囲に対する認識を共有できるように、契約書では、どのような契約類型であるのか、何を目的にしているのかなどといった事項を明記しておくことが重要といえます。
(特に目的条項などできちんと明記しておくとよいです。)
4 損害賠償の範囲の制限
(1)損害賠償の範囲の制限
契約書では、損害賠償の範囲を制限する規定が設けられることが多くあります。
この場合、何を除外するのか、何を含むのかという点について、自らの認識と相違がないように文言を定めておくことが重要といえます。
また、特に除外すべき損害項目がある場合には、その旨を明記しておくことが重要といえます。
例えば、「委託者は、受託者の故意・過失により損害を被った場合、通常損害の賠償を請求できる」というような規定の場合、「特別損害を除いて通常損害に限る。」という趣旨であるのかどうかが不明確であるので、特別損害を除くのであれば、「通常損害に限り」などのように、その旨を明記しておくことが望ましいといえます。
また、例えば、逸失利益は、契約の内容によっては通常損害にも特別損害にも分類され得るものであるので、これを除外したい場合には、「逸失利益は除く。」と明記しておくべきといえます。
(2)定義が不明確な文言の使用は控える
契約書では、「直接かつ現実に生じた」(損害)、間接的損害、付随的損害といった表現が使用されている例があります。これは英文の契約書を直訳したものが、安易に使い回されていることに由来すると思われます。
しかし、民法では、上記のとおり、通常損害・特別損害に関する規定がありますが、「直接かつ現実に生じた」(損害)「間接的」「付随的」という概念はありません。
そのため、「直接かつ現実に生じた」損害、「間接的」損害、「付随的」損害という表現には明確な定義はありません。
委託者としては、不明確な規定により、損害賠償の範囲が狭められてしまうことを防ぐために、このような表現は削除することが考えられます。
他方、受託者としては、制限したい内容をより明確にし、受託者自身が想定する損害賠償の範囲と相違がないように文言を調整するべきといえます。
5 損害賠償額の上限
契約書では、「損害賠償額は、委託料を上限とする」などといった上限規定が設けられることがあります。
損害の範囲と、損害額は、区別して考えます。
損害の範囲は、どのような損害が損害賠償の対象として認められるかという問題であり、損害額は、これらを金銭評価した場合の金額の問題です。
損害賠償額に上限を設定すると、通常損害・特別損害などといった損害の範囲に基づき算定された金額に、上限が付されるので、損害の範囲にかかわらず、損害賠償が可能な上限額が明確になります。
特に、業務委託契約において、「委託料を上限とする」という規定があれば、委託料が前払いされている場合にはその委託料を返金し、後払いの場合には委託料を0にすればそれ以上の損害賠償を負わないことになります。
契約交渉では、損害の範囲として含まれるのはどのような損害であるのかという観点と、損害額の上限はどのように設定されるべきかという観点の両面から損害賠償条項を定める必要があります。