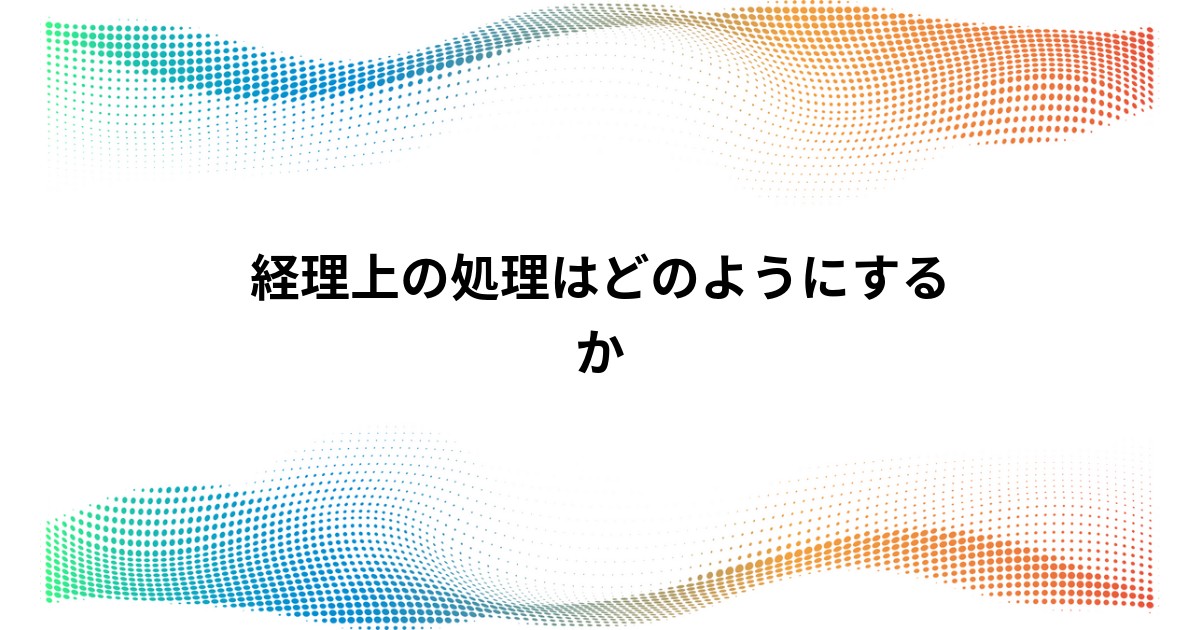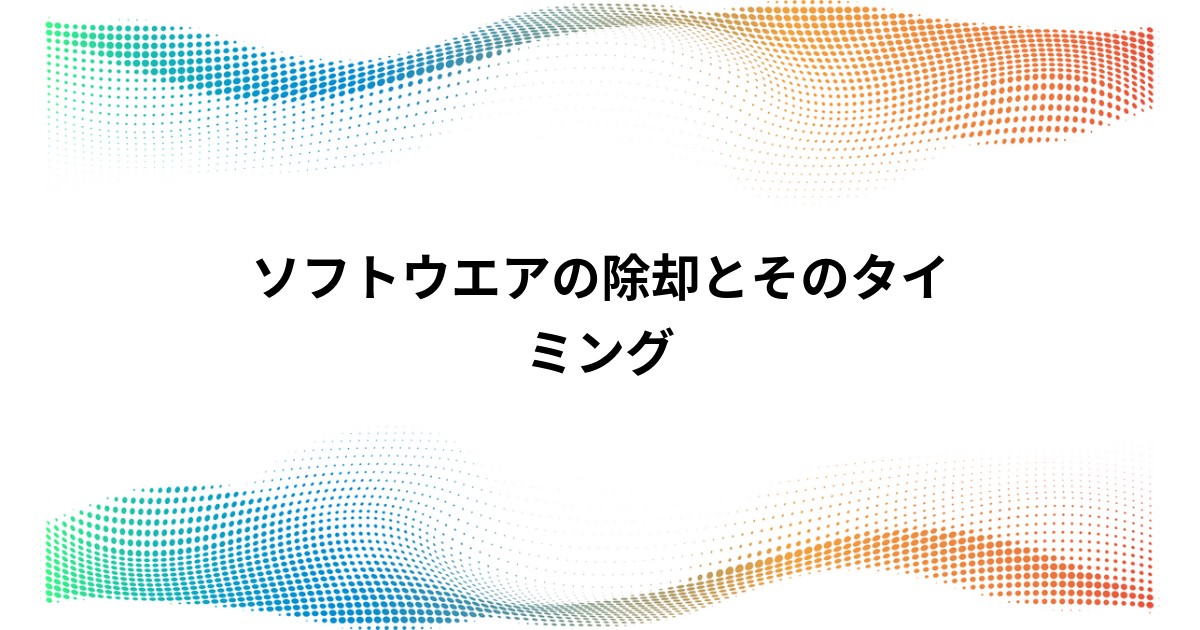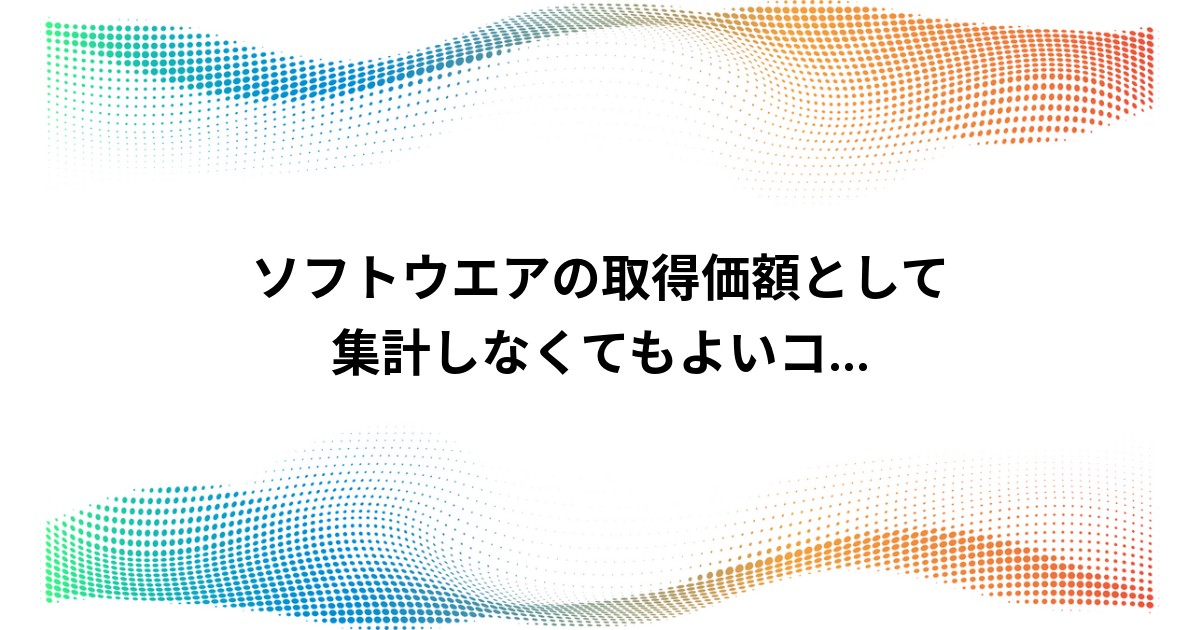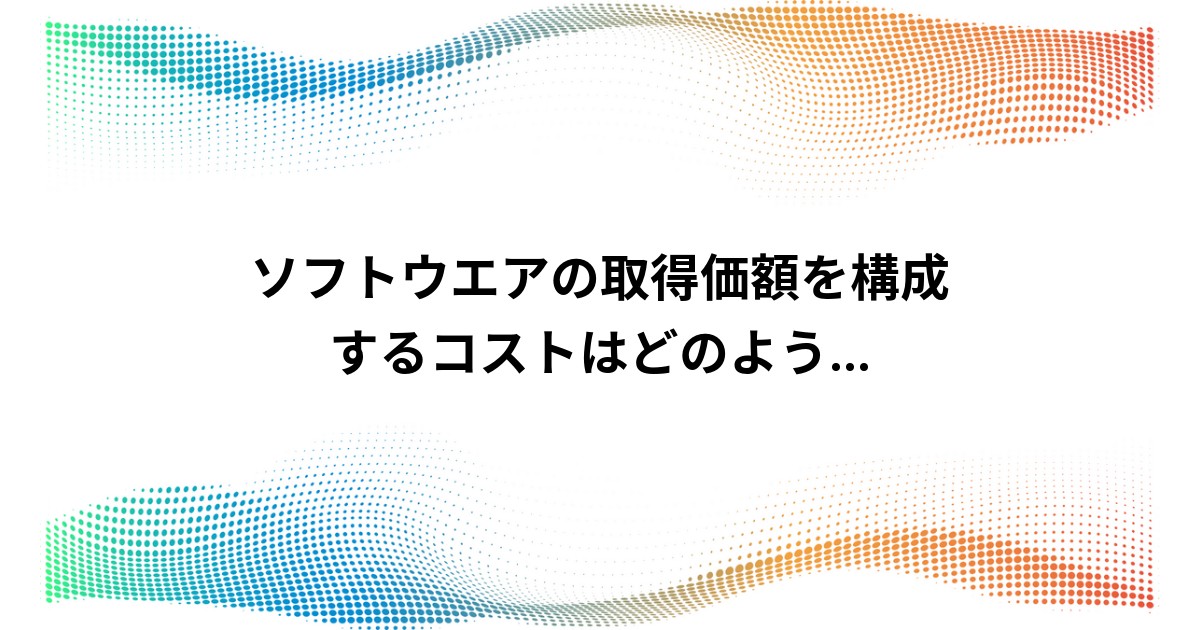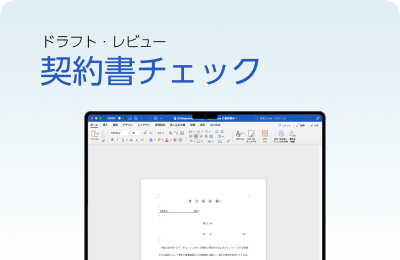ごくごくありふれた製造業の事業スキームをイメージすると,まず設備を作り,モノを生産し,これを販売するというプロセスをたどります。つまり,まず費用が先行して発生し,それから収益(売上)が発生する。極端に言えば,大赤字から黒字ということになります。
会計的発想
確かに,設備投資は最初に一挙に発生しますが,その費用は,そもそもこれからモノを作り,収益を上げるために投資したのです。つまり,ソノ費用は将来の収益を獲得するために先行して発生しているのです。とすれば,設備投資コストは,将来の収益と対応させるべきであって,発生したときに一度に費用にするのは妥当でないということになります。
よって,その「将来の収益と対応させるべき設備投資費用」は,収益の発生に貢献するであろう「期間」にわたって,一定の「規則的方法で費用にする」のが妥当という発想になります。この「設備投資費用」を固定資産の取得価額といい,「規則的方法で費用にする」ことを減価償却といい,「期間」を耐用年数といいます。
そして,どのような方法で,またどのくらいの期間で減価償却するかは,一般的に公正妥当と認められる範囲であれば,企業の実態(資産の利用状況など)に応じて決めるべきです
税務的発想
設備投資費用を全額その期間の損金(費用)にしてしまうことができれば,例えば,儲かりまくっている企業が期末直前に大量の設備投資をしていくらでも所得(利益)を圧縮して節税ができてしまいます。これを防止するため,あらかじめ設備投資といえそうな財(固定資産)を指定して,一時に損金とすることができないようにし,何年かに分けて損金にさせます(減価償却)。
そして,固定資産ごとに何年で消却するか(耐用年数)を指定します。これにより,税務当局が認める各期の減価償却費が決定され,その額を限度に損金として認められる(損金算入限度額)ということになる。これらのルールより,課税の公平が保たれるのです。
これによれば,ある期の損金算入限度額が10だとして,経理上は減価償却費を30計上していても,限度額を超過する20は税務上損金として認められず,申告書で調整(加算)します。一方で,経理上減価償却費を5計上しても,税務上は企業が経理した5までしか認めません。
なぜなら,もともと10まで損金にすることを認めているところで企業が(うっかりであっても)少なく計上したのに,これを当局が認める必要がないからです(結果的にその分所得が増えて納税額が増えます)。
実務上の問題点
固定資産については,企業はほとんどすべて税務ルールに従っています。これは決してネガティブなことではありません。特に,独自に耐用年数を定めるとはいっても,現実には難しいし,耐用年数は長いものは数十年に及ぶため,もし税務ルールと異なる処理をした場合 ,その間ずっと法人税の申告書で調整計算を行わなければなりません。
それなら,税務ルールどおりにやれば楽といえば楽です。このようにすれば,会計と税務の数値は一致します。
しかし,上述のとおり,固定資産の減価償却については,たまたま結果的に同じことがあっても,会計と税務は目的が全く異なることに留意すべきです。
例えば,どうしても黒字を出したい企業があるとします。しかし,減価償却費を計上すると赤字になってしまうとします。このとき,会計からすれば,赤字であっても赤字になろうとも減価償却は規則的に行わなければならないのであり,期によって減価償却費を計上したりしなかったりするのは,まさに粉飾であり,一般に公正妥当とは認められない。
一方,税務からすれば,減価償却は書く期の限度額以内で損金として認めるに過ぎないので,ゼロにしようがお咎めなしということになります。以前筆者(深作会計士)は,税理士会にこの点を寄稿したところ,「赤字なのに減価償却費を計上するなんて頭がおかしいんじゃないのか?」と大マジメに反論する税理士がいましたが,そういう発想や思考回路になるのはやむ終えないと思われます。
確かに,固定資産における税務上のルールは,課税の公平を目的とし,相応の客観性がありますが,それはあくまで標準的な利用状況を目安にしたものです。同じ固定資産といっても,企業の利用状況はさまざまであるため,そのままあてはめられないこともあります。
また,外資系企業などでは,減価償却の方法がグロ^ーバルに統一され,これに従って処理を強制されることもまれでなく,この場合には,日本の税務ルールと一致しないことになります。
かといって,別にあわてるまでもありません。どうして会計と税務が分離せざるを得ない場合には,きちんと申告調整すれば足りるのです。