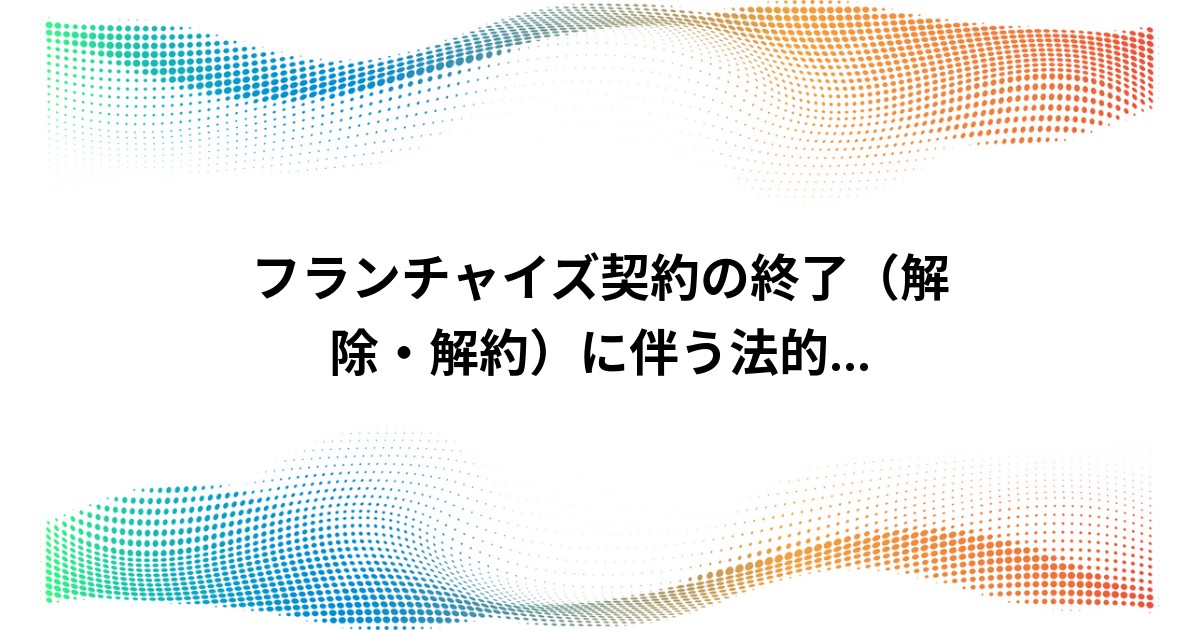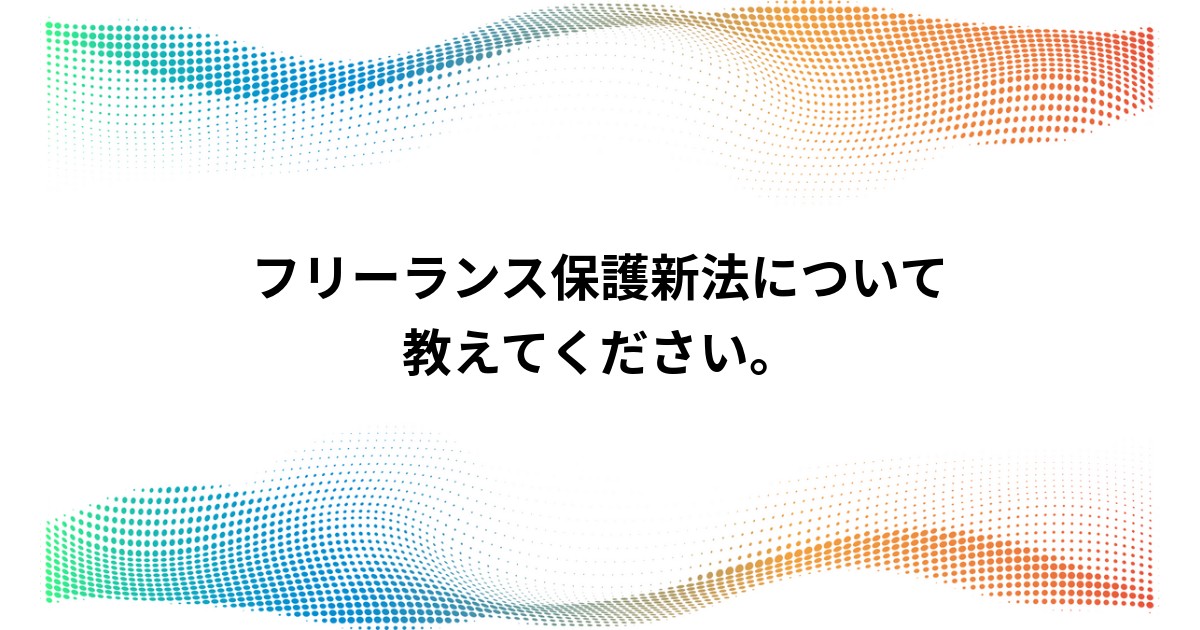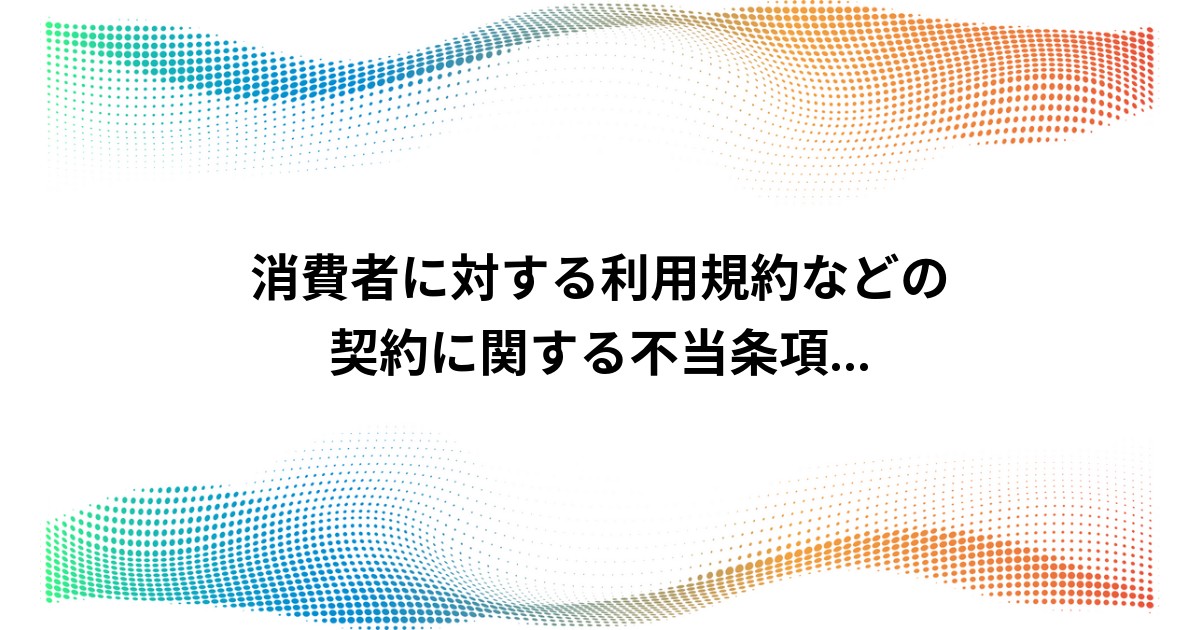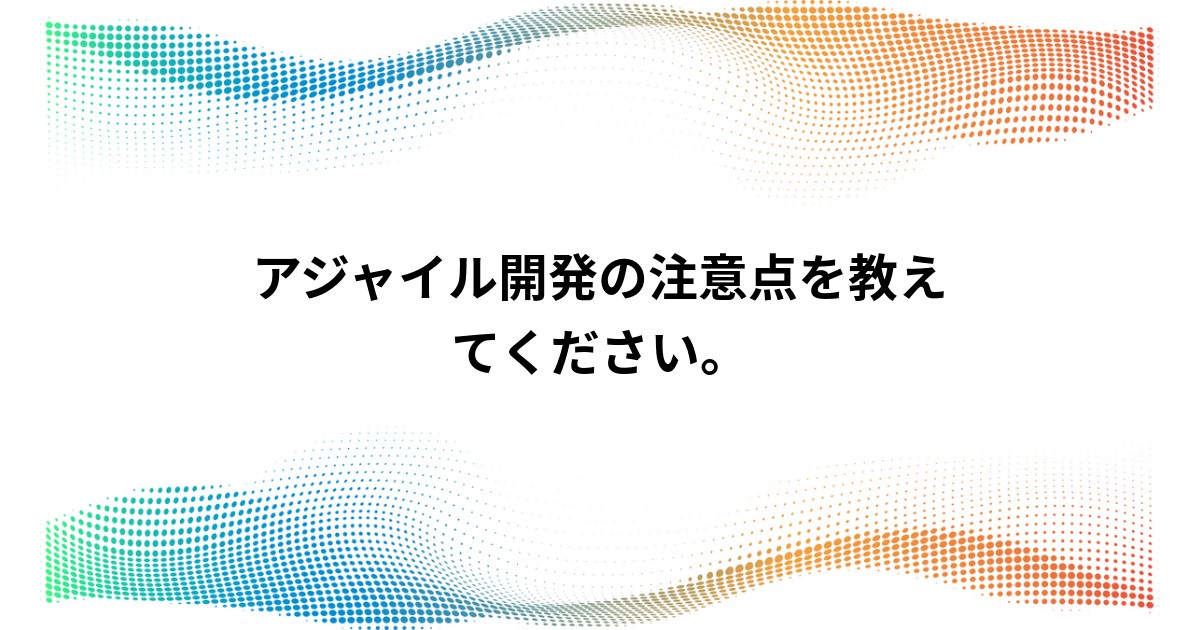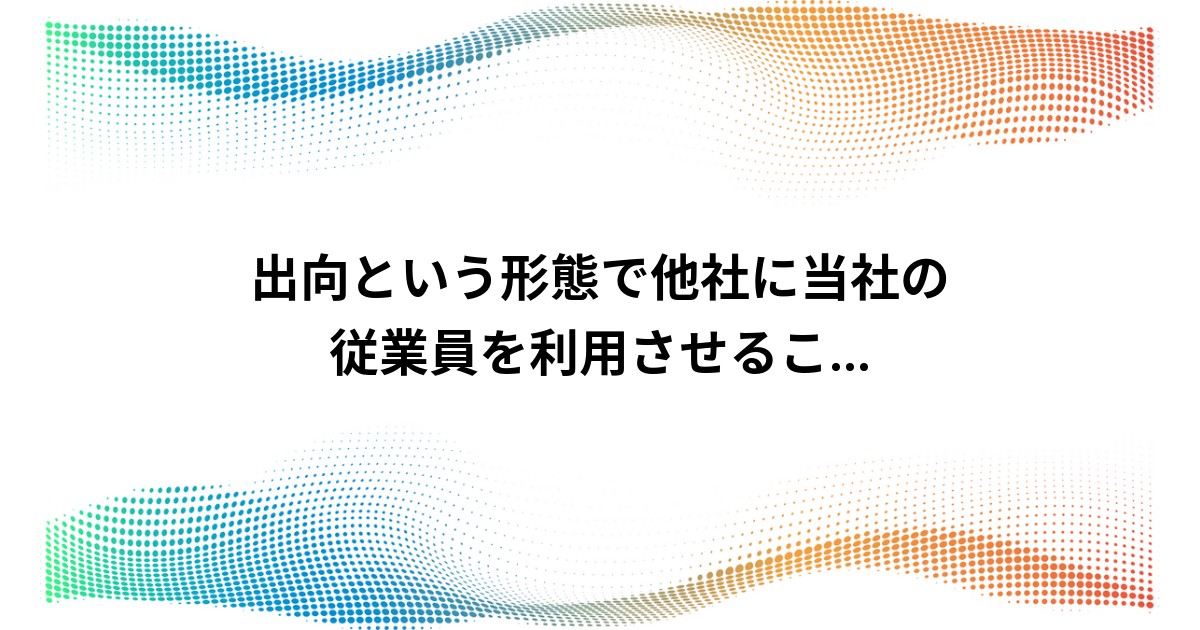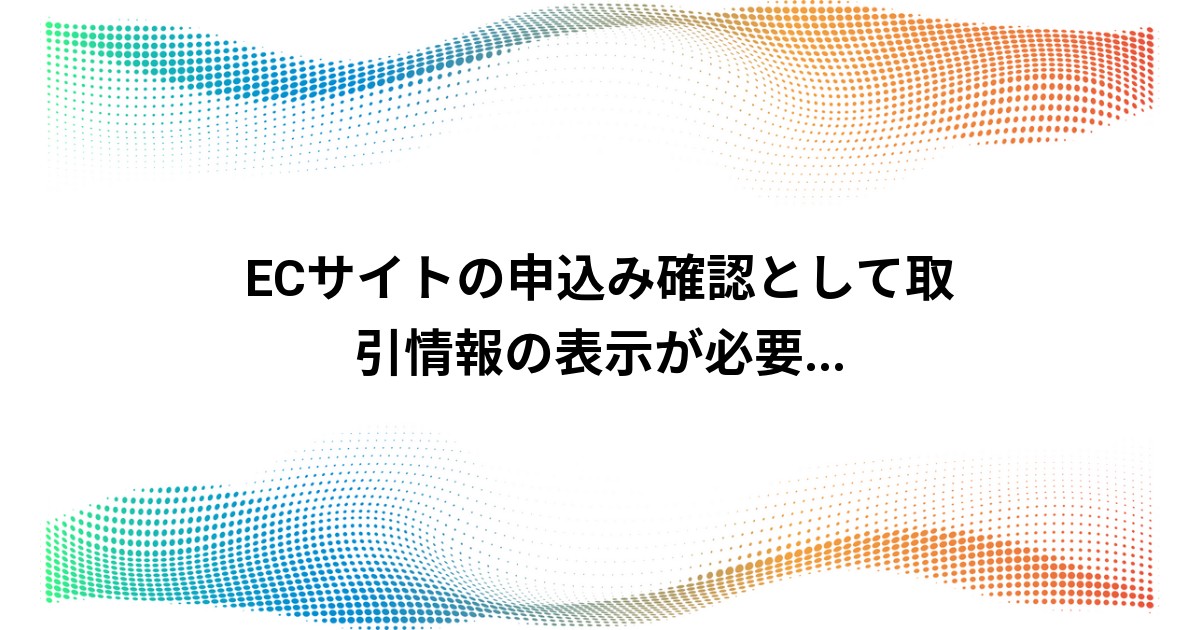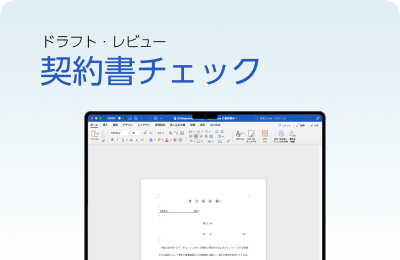1 製造物責任とは
製造物責任は、製品に欠陥があり、それによって被害が生じた場合、その製品を製造した業者等が、その製品の欠陥によって発生した損害について損害賠償責任を負うというものです。
例えば、購入した電気機器が発火し、その購入者が怪我をした場合には、製造業者等に対し、製造物責任に基づいて、損害賠償請求をすることができます。
もちろん、製造物責任がなくても、一般的な不法行為責任や債務不履行責任等により、このような損害については賠償請求することができる場合があります。
しかし、後述するとおり、一般的な不法行為責任や債務不履行責任よりも、責任の追及が容易になっているという特徴があります。
製造物責任は、民法等の一般的な責任に加えて、製造物責任法(以下「法」といいます。)で特に定められています。
2 製造物責任の留意点①(被害者の立証が容易)
製造物に基づいて、損害賠償請求をする被害者は、一般的な不法行為に基づくと、以下を立証することになります。
・メーカーに過失があること
・損害が生じたこと
・損害がメーカーの過失により生じたこと
しかし、製造に関与していない被害者にとって、「過失」があることに関する証拠を収集することは難しく、立証が難しいところです。
「過失」とは注意義務の違反をいうので、どのような注意義務があり、どのような注意義務に違反をしたのかを被害者が特定し、これを立証しなければなりません。
被害者は、異常が生じたその製造物しか資料がないこともあり、この立証は非常に難しいといえます。
そこで、製造物責任では、製造物に関する損害賠償請求においては、以下の立証があれば責任を認めます(法3条本文)。
・製品に欠陥があること
・損害が生じたこと
・損害が欠陥により生じたこと
「欠陥」とは、「製造物が通常有する安全性を欠いていること」をいいます(法2条2項)。
例えば、「通常の使用をしているのに発火してしまうようなテレビ」があるとすれば、これは通常の安全性を欠いているので、「欠陥」ありといえます。
製造物責任法によって、この欠陥さえ立証すれば、「過失」があることまでの立証は不要になっています。
3 製造物責任の留意点②(製造物の意義)
「製造物」とは、製造又は加工された動産をいいます(法2条1項)。
この定義のとおり、動産ではないソフトウェアやサービスは製造物責任の対象になりません。
4 製造物責任の留意点③(欠陥の意義)
「欠陥」=「製造物が通常有する安全性を欠いていること」があるかどうかは、以下の要素により判断されます。
・当該製造物の特性
・その通常予見される使用形態
・その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期
・その他の当該製造物に係る事情
上記のように、「製造物の特性」や、「通常予見される使用形態」が検討されますので、製造業者等は、以下のような点を特に留意するべきといえます。
・製造物を製造・流通させることにより、どのような人がどのような使用をするのかを十分に想定し、これらの人にとって安全性を欠いていないかを検討すること。
・製造物を使用する人にとって必要十分で、かつ、分かりやすい指示・警告がされているかを検討すること。
・同種の製品においてされている安全対策がとられているか。
5 製造物責任の留意点④(責任を負う者の範囲)
製造物責任に基づいて責任を負うのは、以下のものです(法2条3項1号乃至3号)。
・製造業者
・輸入業者
・表示製造業者
OEMで製造委託した者は、自ら製造をしていません。
しかし、製品に自社ブランドを表示するので、「表示製造業者」として製造物責任を負います。
6 製造物責任の留意点⑤(消滅時効)
製造物責任は、以下に定めるときのうち、より早く到来したときに消滅時効にかかります。
・損害及び賠償義務者を知った時から3年間行使しないとき。ただし、人の生命または身体を侵害した場合は、損害及び賠償義務者を知った時から5年間行使しないとき。
・製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年間が経過したとき。
7 OEM契約における製造物責任
OEM契約では、自社ブランド製品の製造委託する事業者(製造委託者)も、これを受託して製造する事業者(製造受託者)も、製造物責任を負います。
このため、第三者に損害が生じた場合、第三者は、製造委託者にも、製造受託者にも責任追及することができます。
このような場合が生じたときに、どのように解決するべきかについて、OEM契約の製造物責任規定において定めておくことが望ましいといえます。
特に、いずれかが責任追及を受けた場合にどのように解決していくのか、またはいずれかが損害賠償をした場合に、相手方にどのように求償できるのか、などを定めておくとよいです。
製造委託者としては、自らはブランドを付しているだけであって、製造や加工に関与していないにもかかわらず、製造物責任により責任追及を受け、これを賠償しなければならないことになってしまいます。
そこで、以下のような規定を盛り込むように交渉することが考えられます。
・第三者から製造物責任の追及を受けた場合には、製造受託者の責任と費用により、これを解決すること
・製造委託者が損害を賠償した場合には、受託者に全額を求償することができること
もちろん、製造委託の報酬額や、製造物の内容、製造委託者の関与の度合いによっては、製造受託者において上記をそのまま受け入れることは難しい場合もあります。
製造物責任の内容を踏まえて、妥当な責任の分界点を探っていくことになります。
8 製造物責任保険
上記のような契約を交わして求償ができる条項を盛り込んだとしても、必ずしも安心ではありません。
製造受託者の資力がなければ求償に応じられない場合もあります。
このような場合に備えて、製造物責任が生じ得る製品については、製造物責任保険への加入によるリスク軽減も検討するべきです。