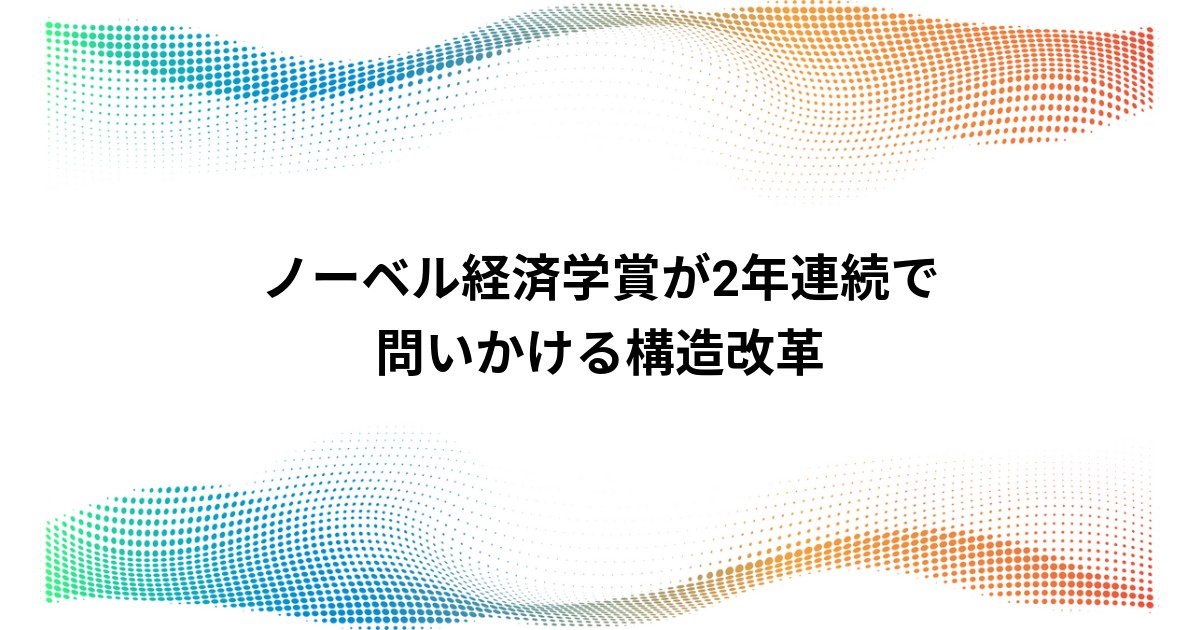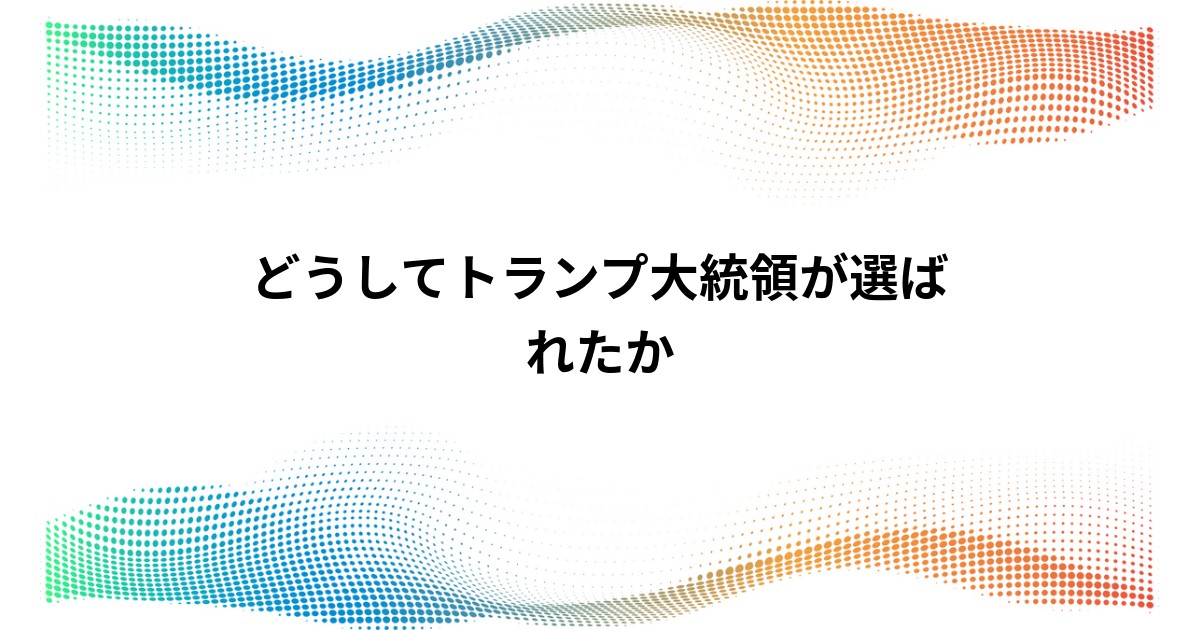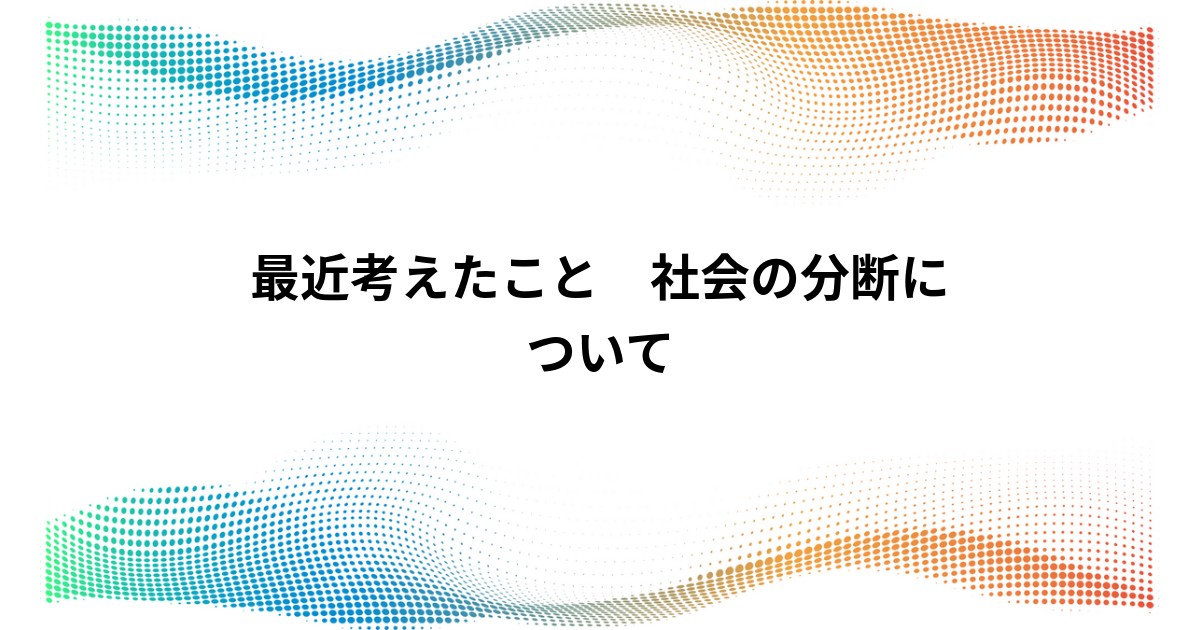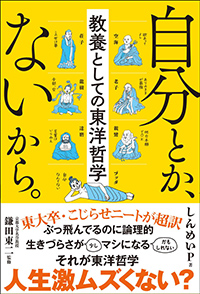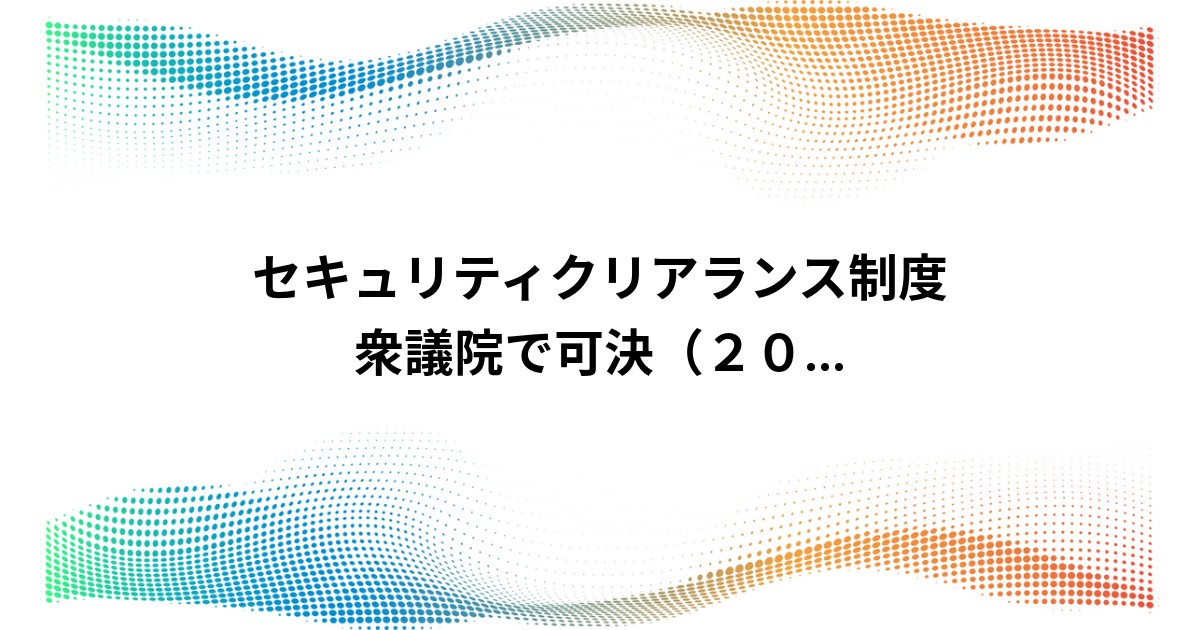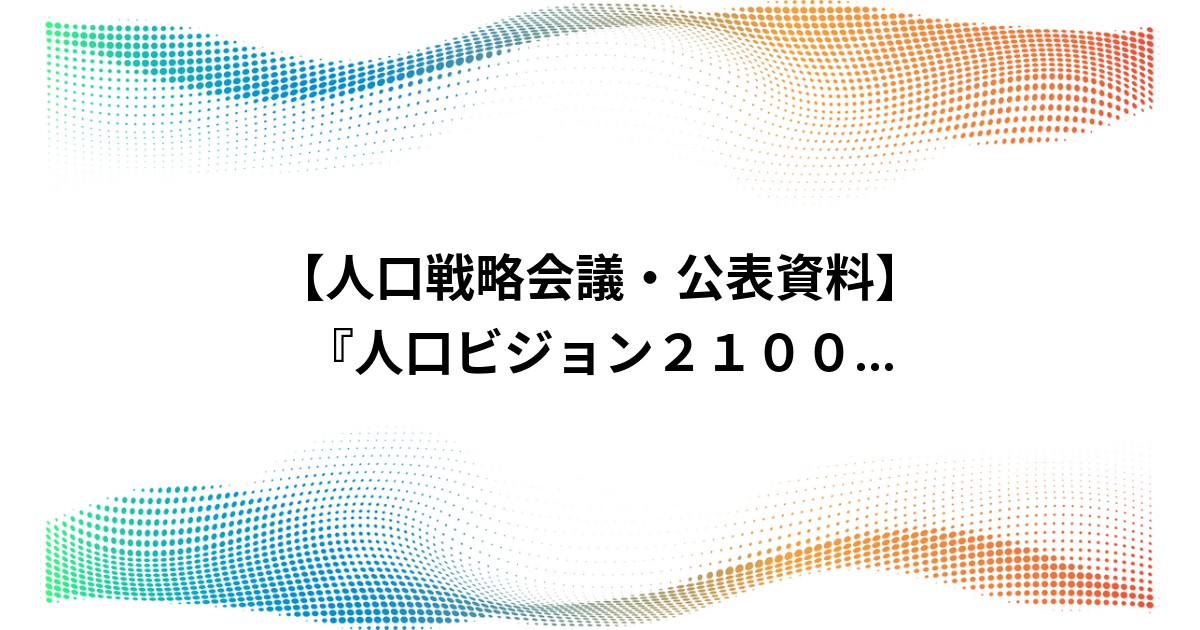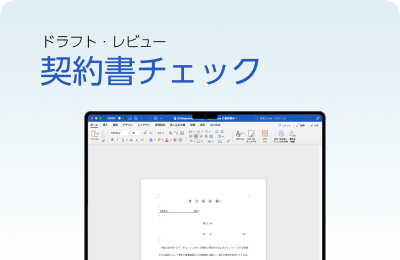2025年のノーベル経済学賞は、米ノースウエスタン大のジョエル・モキイア教授(79)と仏コレージュ・ド・フランスのフィリップ・アギヨン教授(69)、米ブラウン大のピーター・ホーウィット教授(79)らが受賞した。
授賞理由は「イノベーション、経済成長、および創造的破壊のプロセスに関する研究」。
彼らのモデルによれば、経済成長は新しい、より優れた製品や生産技術が、市場の既存のものを絶えず打ち負かしていくプロセス(創造的破壊)によって達成されるという。
ある企業が画期的なイノベーションを生み出すと、一時的に独占的な利益を得る。この大きな利益が、次のイノベーションを生み出そうとする企業へのインセンティブとなり競争を加速させる。
この新しい技術は、やがてさらに優れたイノベーションによって「破壊」され、古い産業や製品は市場から押し出されていく。
この連鎖と既存の産業の置き換えこそが、経済を停滞させずに成長させるためのエンジンであり、国家の繁栄に不可欠な要素だという。そして、このスパイラルが守られるように、競争政策と特許制度は設計されるべきであると主張する。
・ 競争政策: 競争が少なすぎると企業の努力が怠慢になり、多すぎるとイノベーションの成功から得られる利益(一時的な独占)が小さくなりすぎて、研究開発への投資意欲が失われる。競争当局は、イノベーションを促すのに最適な中程度の競争水準を維持する必要がある。大企業による潜在的な競争相手(スタートアップ)の買収(キラー買収)は成長を阻害する。
・ 特許制度: 特許保護が強すぎると、その後の更なるイノベーションを妨げる可能性がある。特許制度は、発明者への適切な報酬と、後続のイノベーションを阻害しない程度のバランスを取る必要がある。
このような主張(2025年)は、長期的な経済成長において「制度」が果たす役割に注目している点で、2024年のノーベル経済学賞「社会制度が国家の繁栄に与える影響の研究」(ダロン・アセモグル、ジェイムズ・A・ロビンソン、サイモン・ジョンソン)と同じ文脈にあり、2024年の主張は2025年の大前提となっていると理解することもできる。
2024年受賞者のアセモグル教授らの著書「国家はなぜ衰退するのか/Why Natons Fail」は、数多くの歴史的な事例や現在の状況が詳細に論じられている。
日本人にとって身近に感じるのは、朝鮮半島の例だ。
南北に分断された1948年当時、主要な産業施設(重工業、化学工業、電力設備など)のほとんどは、北部に集中しており、北には石炭や鉄鉱石などの天然資源も豊富にあった。南は、主に農業が中心で工業基盤は脆弱だった。その後の南北の経済成長が大きく逆転したのは、北の「収奪的な制度」と、南の「包括的な制度」の選択が、人々のイノベーションへのインセンティブと投資を分けた結果だという。
広く市民の所有権を保障し、誰もが平等に経済活動に参加できる機会(インセンティブ)を与える制度(包括的な政治制度・Inclusive Institutions)のもとにおいては、自由な経済秩序が構築され、政治制度と経済制度のよい循環が続いていく。
逆に、少数のエリートが富や権力を集中させ、大衆から利益を吸い上げる構造(収奪的な政治制度・ Extractive Institutions)のもとでは、経済制度も収奪的となり、負のスパイラルが生じ、長期的な技術革新と成長が妨げられるという。独裁的な権力者は、創造的破壊によって、新しい富やそれにともなうパワーを持つ者が現れるのを嫌う。そのような者は権力者の地位を不安定にしかねないからだ。
そのような権力者にとっては、自分と側近だけが豊かであれば、その他大勢は貧しく力がない状況が好都合なのだ。
残念ながら、多くの国のリーダーは、自らの保身のために収奪的な政治制度を選ぶ。政治は腐敗し、国は貧しいままとなる。
最近、民主主義より全体主義(王政)の方が、意思決定が早く、決定される内容が合理的であれば経済成長が早いという主張もあるが、アセモグル教授らはこれに否定的だ。
権力に結び付いた利権を守ろうとすることが、社会経済を停滞させるとすれば、同じ政権が長期間続くことは望ましくない。
政治制度がそれほど経済制度とその発展に影響があるのであれば、つまり国民生活を豊かにすることも停滞させることもあるとすれば、前政権に絡みついたしがらみを断ち切り、不正を明るみに出すためには、新しい政権がどうであれ、政権はたまに代わる方がよいことになる。
政治の清廉さが、経済制度に深くかかわるのであれば、政治家のコンフリクト(利益相反)は許されないことを徹底すべきことになる。
贈収賄などは勿論、親議員が作った多額の政治資金を持つ政治団体を息子・娘議員が非課税で承継できることなどは、課税の潜脱であり、これから政治家を目指す人々にとって不平等な障壁だ。
このような権力の固定化に一役買っている制度(反包括的な政治制度)を残しておくと、経済制度もその分収奪的になるはずだ。
国家は、人々の共同主観的現実であり、一つの団体なので、このような考え方は、企業などの団体にも当てはまるように思う。
つまり、少数のエリートが富や権力を集中させている会社は、長期的には成長しない。利己的な社長と取り巻きがマネージしている会社は、長期的には成長しないということだ。
合掌