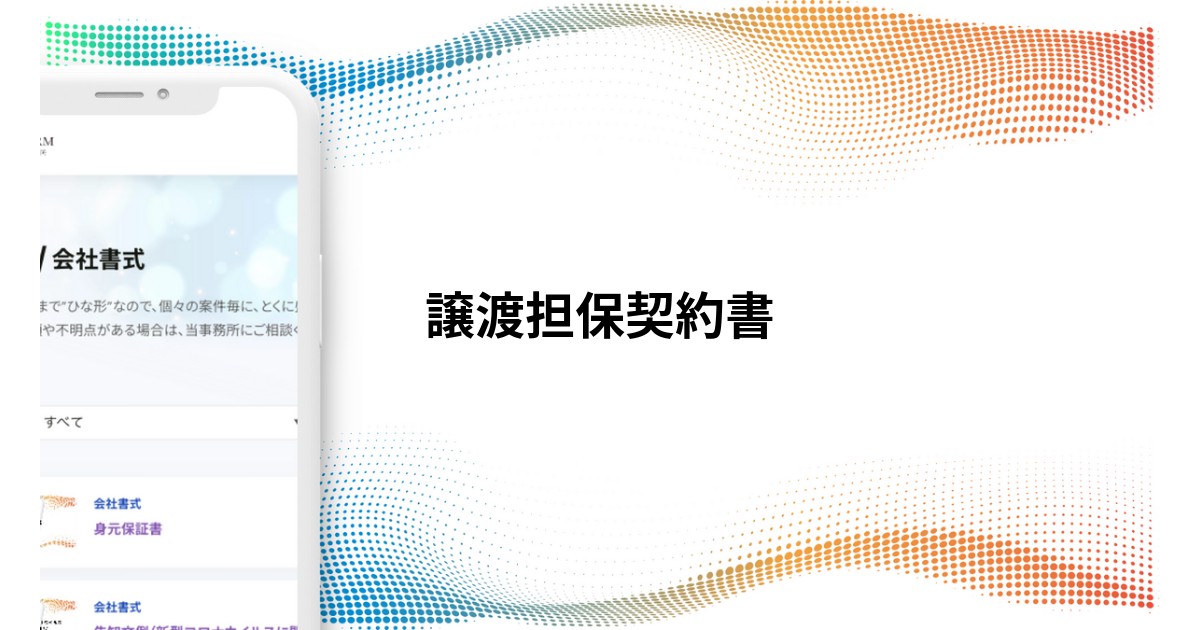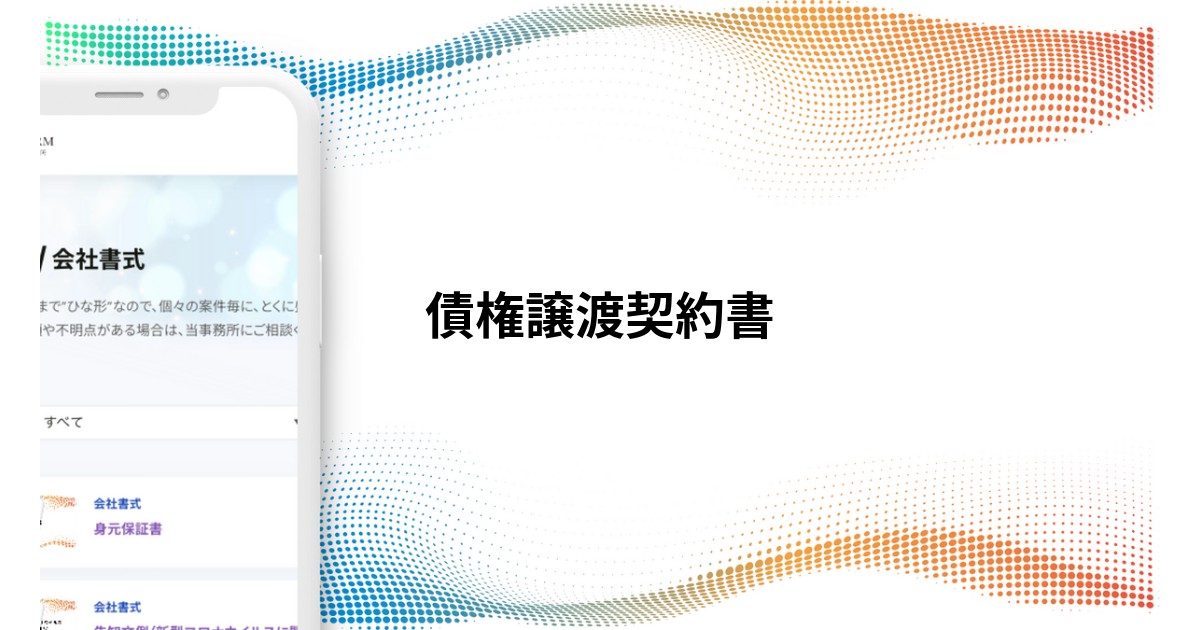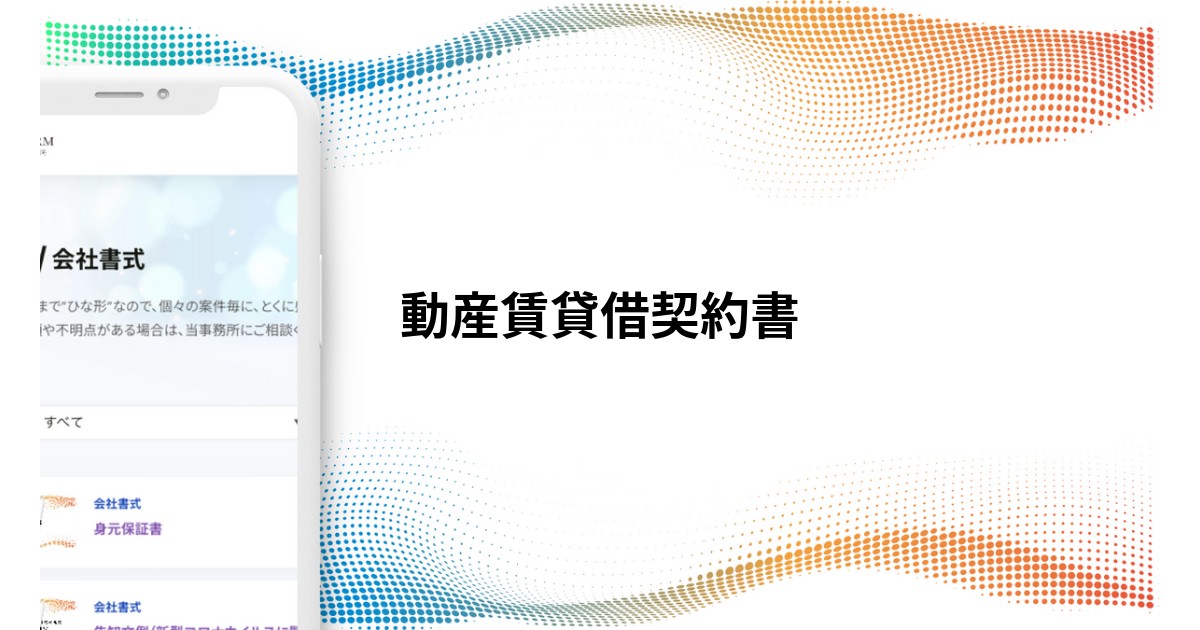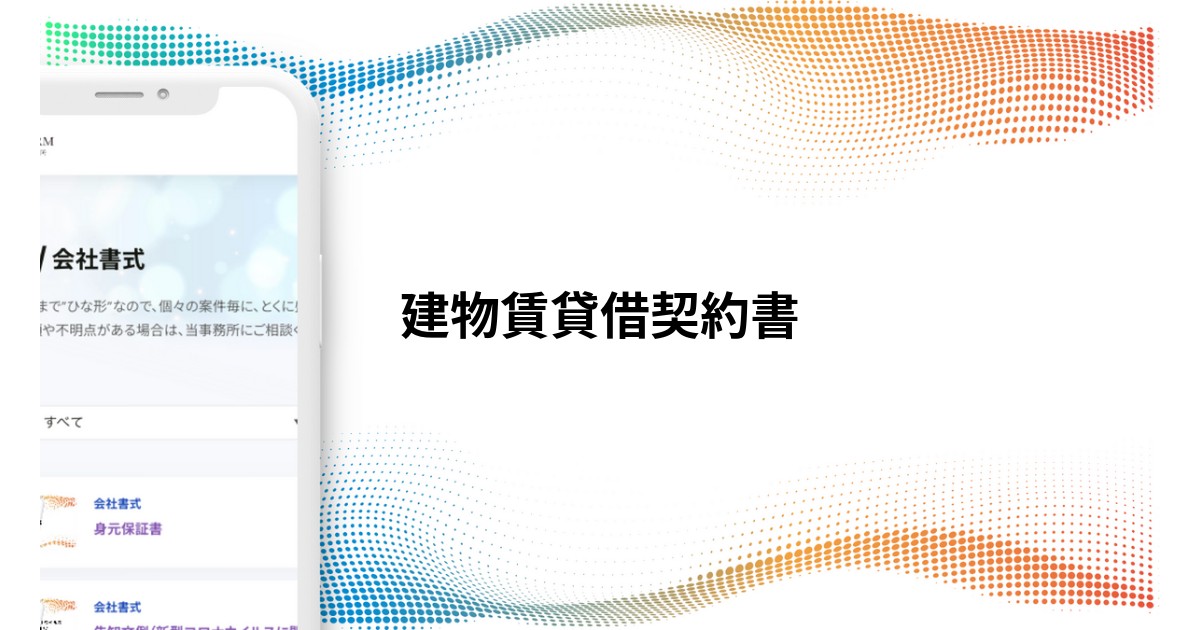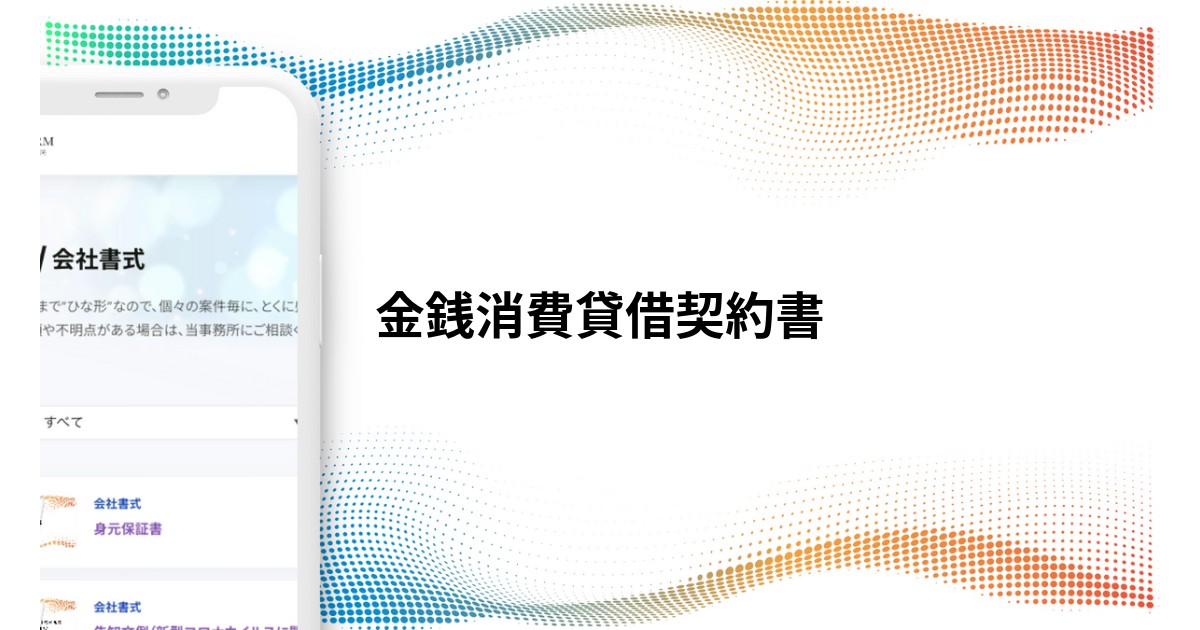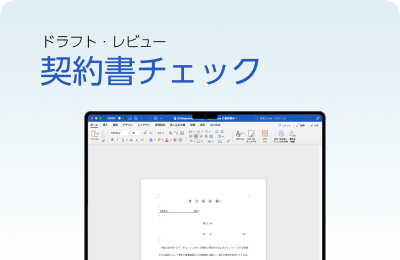金銭消費貸借契約(保証人条項付)の実務上の注意点
1 契約を口頭や簡易なメモで済ませると、紛争時に貸付けや条件を証明できず債権回収が困難になる場合があります。
2 利息制限法の上限利率(年15〜20%)を超える利息は無効であり、超過利息は返還請求の対象になります。特に、出資法の上限利率(年20%)を超える金利契約は刑事罰の対象となります。
3 継続的に不特定多数に対して金銭を貸し付ける場合、貸金業登録が必要となり、無登録営業は刑事罰の対象となります。
4 期限の利益喪失条項を適切に設定しないと、債務者に信用不安が生じても一括返済請求ができません。
5 債務者の支払いが滞った場合に備え、公正証書(強制執行認諾文言付)を作成していると判決などの債務名義の取得手続を省いて迅速に債権回収できる場合があります。
6 返済期日から原則として5年で債権が消滅時効により消滅します。債務者の支払が遅延しているときは定期的な弁済確認や債務承認で時効を中断する必要があります。
7 保証契約を書面で行わない場合、保証契約が無効になります(民法446条2項)。また、個人が事業資金の保証をする場合、保証意思宣明手続(公正証書作成)を踏まないと保証契約は無効となります(民法465条の2以下)。
8 無利息貸与、返済期限未設定、返済実績が乏しい場合は、税務上、貸付けではなく贈与と認定され、高額な贈与税が課される可能性があります。
9 契約書への収入印紙の貼付を怠ると印紙税法違反となり、過怠税が課されます。 国税庁の印紙税額一覧表の1号を参照してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
10 個人(給与所得者、公的年金受給者)が貸付けを行い年間20万円以上の利息を得た場合、「雑所得」として確定申告義務が生じます。
11 借主(法人)が非居住者に利息を支払う場合、国内源泉所得として源泉徴収義務が生じます。
12 法人が役員・従業員に低利または無利息で貸付けると、みなし給与(経済的利益)と認定され源泉徴収義務が発生したり、法人側に受贈益(寄附金扱い)が認識されることがあります。

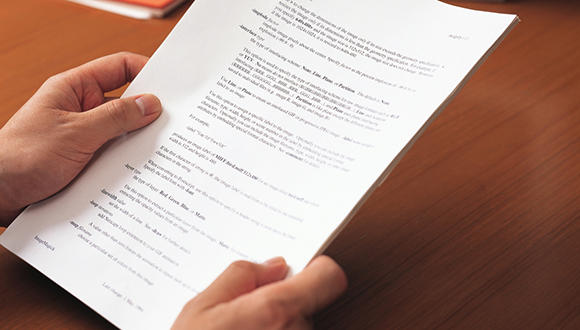
クレア法律事務所では契約書の作成やレビューなどをサポートします。
詳細は契約書(ドラフト・レビュー)をご覧ください。