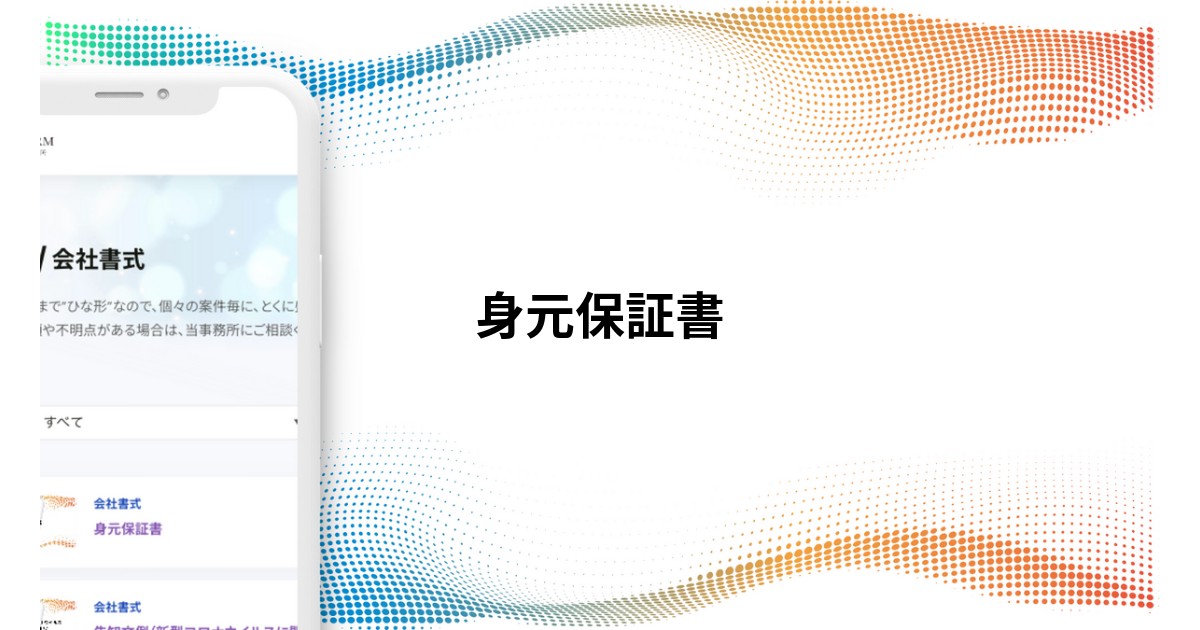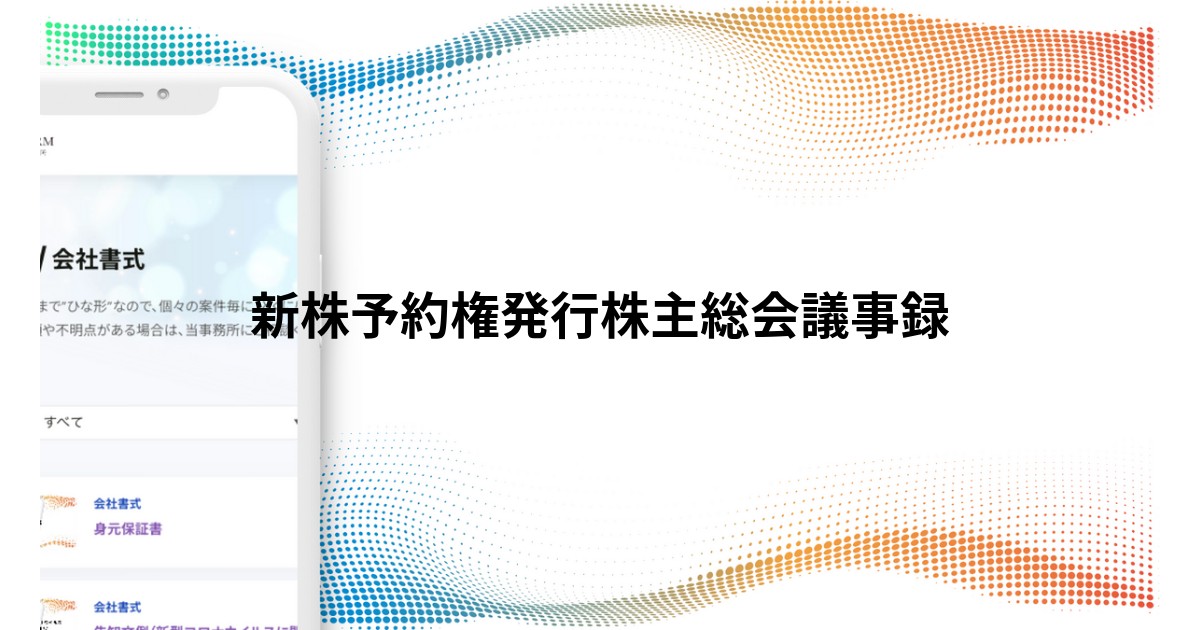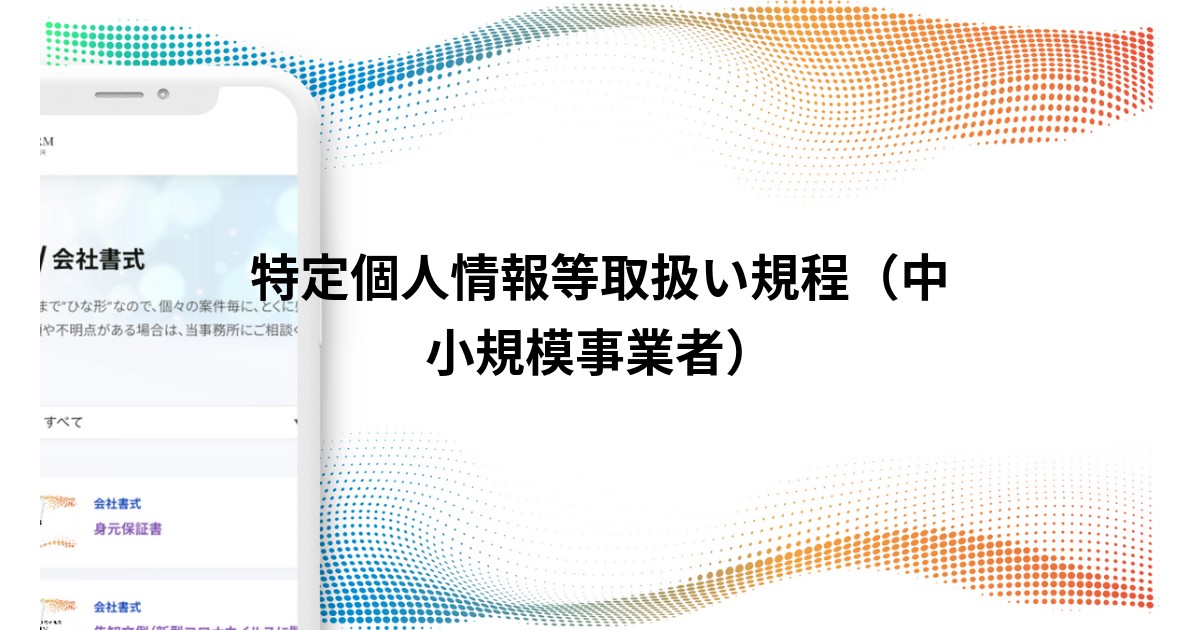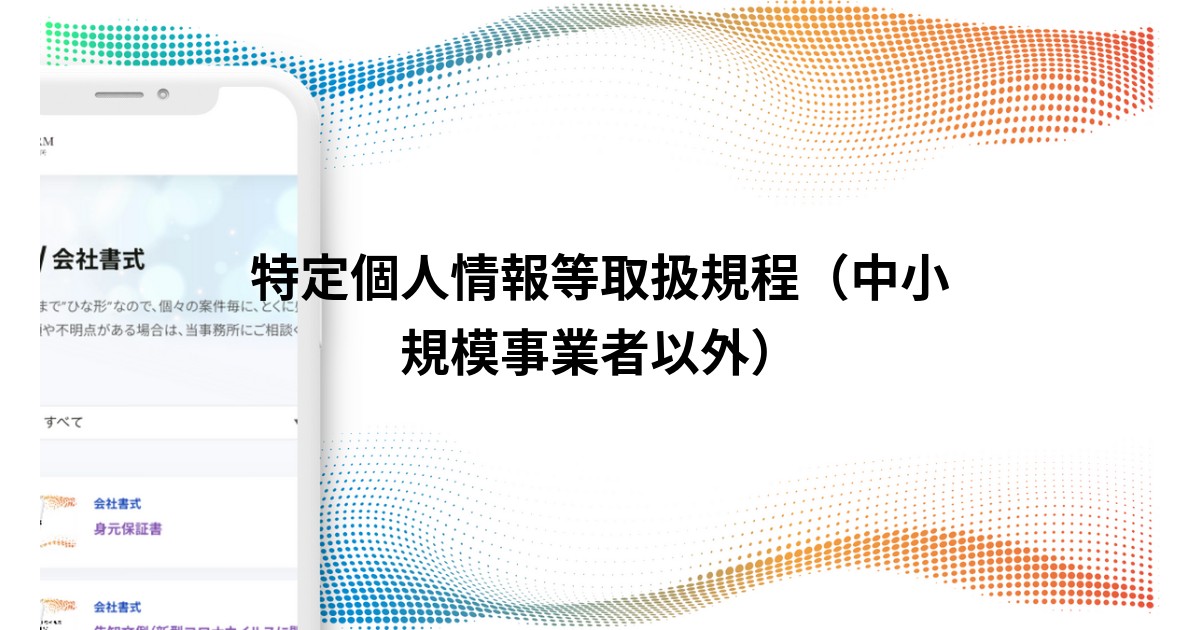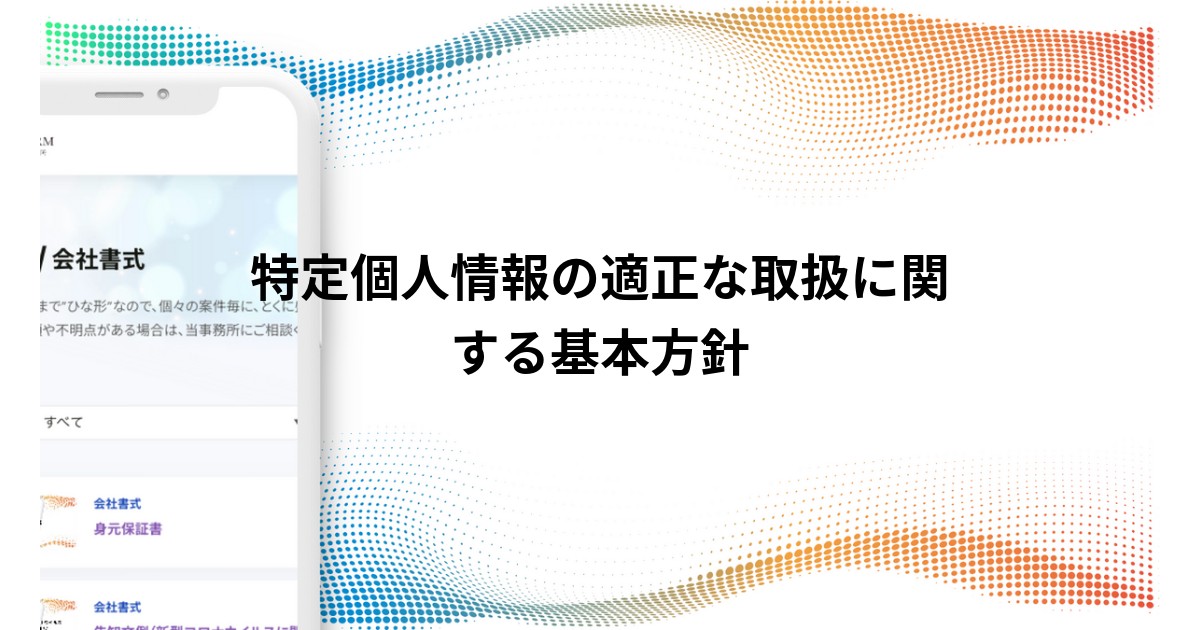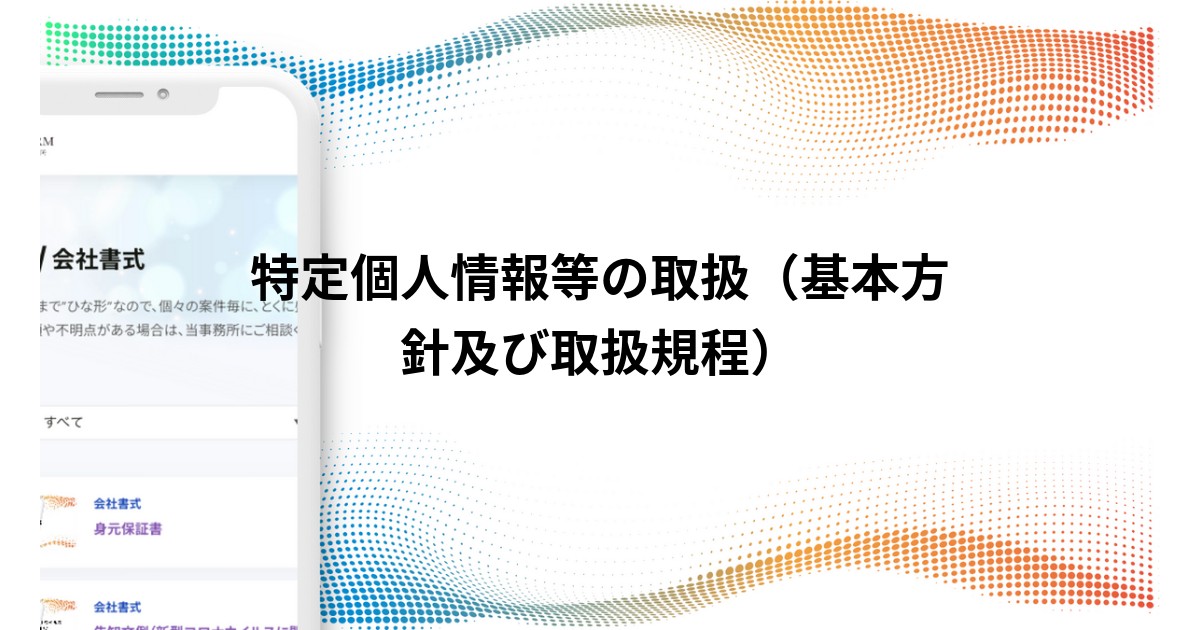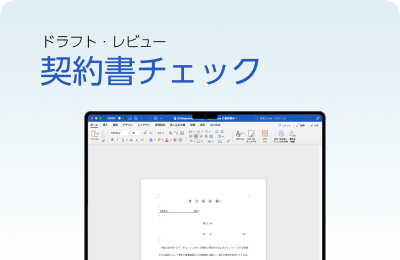目次
身元保証書作成・取得時の留意点
留意点 - 1
身元保証契約は個人根保証契約の一類型であるため書面により極度額(上限金額)を定めなければ無効です(民法465条の2第2項、同3項)。以前は「月額給与の〇年分」と定める例もありましたが、民法の趣旨は根保証人の予見可能性を担保するためなので、変動する可能性のある給与を基準とするより具体的な金額(金100万円)などと定める方が適当だと思料します(当事務所の見解です。)。極度額が高額すぎると保証人を引き受けてもらえず、低すぎると保証契約をする意味が乏しくなるため、双方が合意できる適切な上限額を定めることが重要です
留意点 - 2
身元保証契約は、期間を定めない場合、原則として3年(新卒者などの見習いの場合は5年)とみなされます。3年を超える期間を設定するためにはそれ(最長5年)を定めて書面に明記する必要があります(身元保証法第1条、2条)。
留意点 - 3
身元保証契約は、自動更新とする扱いは許されていません。就業規則等で身元保証の自動更新を定めていても無効となります。もっとも、実務上は初回契約の期間経過後に改めて身元保証書を取り交わすケースはあまり多くありません(3~5年程度無事に勤めれば企業と従業員との間に信頼関係ができるため。)。
留意点 - 4
身元保証契約がある場合でも、会社がそれに安心して従業員の管理を怠ることは許されません。身元保証法は、「裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス。」と定めています。
裁判例では、従業員の過失による損害について保証人に全額ではなく一部(おおむね20~70%程度、中央値は30%程度と思われます)の賠償責任のみを認めるのが通例です。したがって、身元保証はあくまで補完的なリスクヘッジと位置付け、日頃から適切な社員教育・業務管理や不正防止策を講じておくことが肝要です。
本ひな形もそのような趣旨に基づいて保証債務が生じる場合を、従業委の故意・重過失の場合に限っており、軽過失(うっかりミス)は保証の範囲から除いています。
なお、特に若年の労働者については、身寄りがないなど、身元保証契約をしてくれる人を見つけ難い人もいます。そのような人について身元保証サービスを利用する方法もありますが、そのコストは結局は労働者に跳ね返ることになります。企業としては、採用手続を洗練することによって、身元保証による責任転嫁をしない方向性を目指すことも考えると良いと思います。
以上

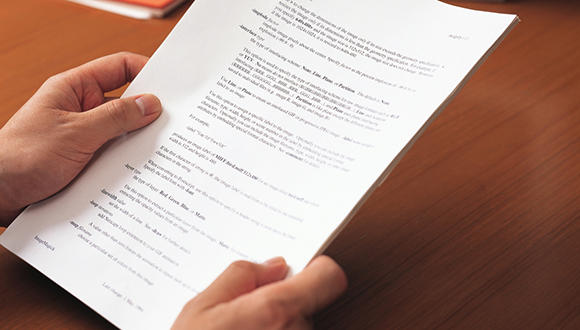
クレア法律事務所では契約書の作成やレビューなどをサポートします。
詳細は契約書(ドラフト・レビュー)をご覧ください。