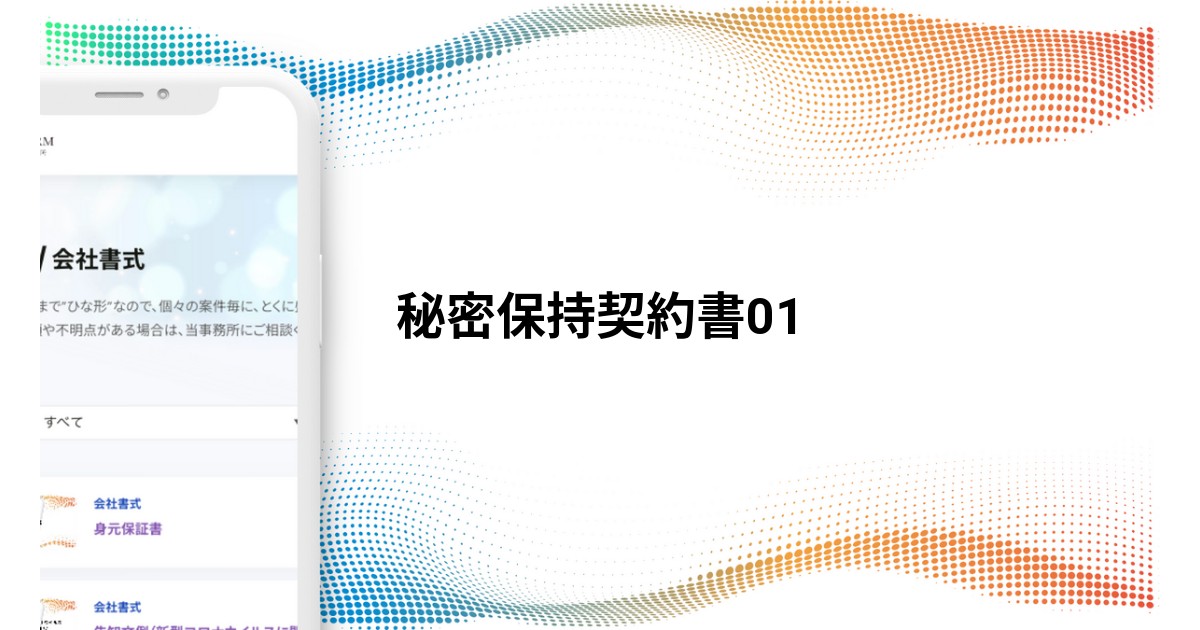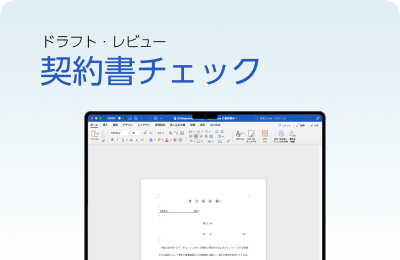秘密保持契約書締結における実務上の注意点
1 秘密情報を守る最も良い方法は開示しないことです。秘密保持契約を結んでも相手方が守るとは限りません。開示する情報は、開示目的に必要な範囲のものに限定して開示するべきです。例えば、実際に相手方と事業を行う前に、協業を検討するために情報を開示するような場合であれば、一般的にはそれほど高度な情報を開示する必要はないと思われます。
2 秘密保持契約では何を「秘密情報」とするかを明確に定義することが重要です。一般的には「利用目的」によってその外延を画し、情報の受領者が当該情報を自社の別のプロジェクトに流用したり、第三者へ提供したりすることを防止します。 トラブル回避のためには、秘密情報はできるだけ特定することが望ましいので、開示した秘密情報は開示秘密情報一覧等の文書を作成して相手方と共有するべきです。情報受領者側としては、既に公知の情報や既に保有していた情報などは、受領時にその旨を告げ、併せて当該一覧から削除することを求めることになります。 本ひな形では、別紙において、利用目的を特定することとしていますが、別紙に、予め秘密情報や除外される情報を箇条書きにしても構いません。
3 当事者間の打ち合わせで口頭によって秘密情報が開示されることもあります。その場合には、議事録などにおいてそれを特定し、本ひな形第1条1項第2文にあるようにその議事録を一定の期間内(本ひな形では7営業日ですが、実務的には30日等も散見されます。)に通知します。
4 個人情報は公知の情報なので秘密情報の定義から外れます。このため、開示する情報に個人情報を含む場合には、別途秘密情報に準じて情報受領者は個人情報を安全に管理すべき義務を負う旨の記載が必要です。
5 秘密情報を受け取った側が自社外に情報を伝える必要が生じる場合の取扱いも重要です。通常、受領当事者が情報を第三者に開示するには開示当事者の事前承諾が必要とされます。また、やむを得ず協力会社や専門家に開示する場合でも、事前にその第三者と元の契約と同等の秘密保持契約を締結させる、あるいは書面で同等の守秘義務を負う旨の誓約を取得しておく条件を定めます。
6 秘密情報の複製や記録を制限することは、情報の拡散を防ぐために有用です。契約ではしばしば「提供者の書面同意なく複製禁止」と定め、どうしても必要な場合のみ許可制にします。また、契約終了時や情報提供者から請求があったときには、受領側が速やかに情報およびその複製物を返却する義務を規定します。返却が難しい場合に備えて廃棄処分の方法も定め、廃棄した事実を証明する書面提出を求める条項を置くことも実務上重要です。これらの取決めにより、契約終了後に情報が手元に残らないよう徹底し、情報漏えいリスクを低減します。
7 機密保持義務は契約期間中だけでなく、契約終了後にも一定期間存続させる旨を定めるのが一般的です。存続期間は取引内容に応じて設定されます。実務的には3年~5年程度とするケースが多く見られます。ただ、機密性の高いノウハウ(例:コカ・コーラのレシピ)など陳腐化しない情報については無期限に近い取扱いとする場合もあります。その情報が陳腐化して無価値になる(保護する必要がなくなる)のはいつ頃かを検討して期間を定めることになります。
8 秘密情報交付時には、書面等で提供する情報には「機密」「Confidential」等の表示を付すことや、口頭で開示した場合は一定期間内に内容を書面化して相手に通知することは極めて重要です。メール送付時にも機密である旨を明記するのが望ましいです。 たとえ詳細な内容の秘密保持契約書を結んでも、情報を交付する際に秘密表示がなければ、秘密管理されていない情報、つまり公知の情報として扱われ、裁判所で秘密であることを認めてもらえません。

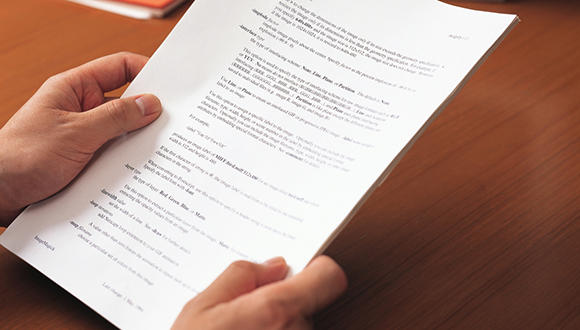
クレア法律事務所では契約書の作成やレビューなどをサポートします。
詳細は契約書(ドラフト・レビュー)をご覧ください。