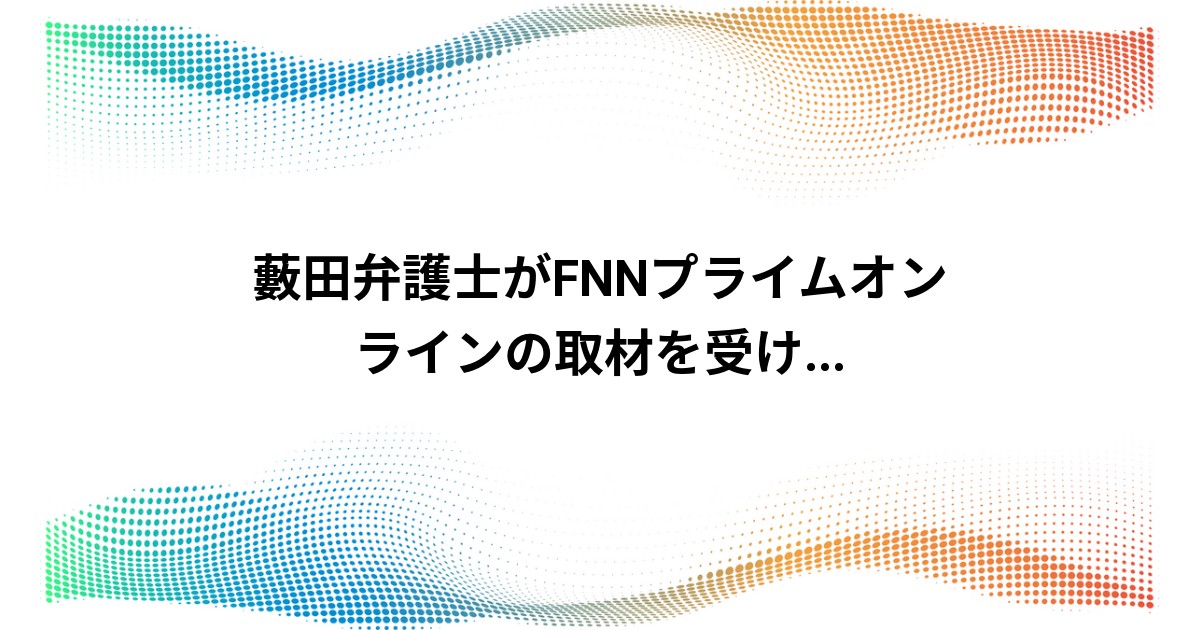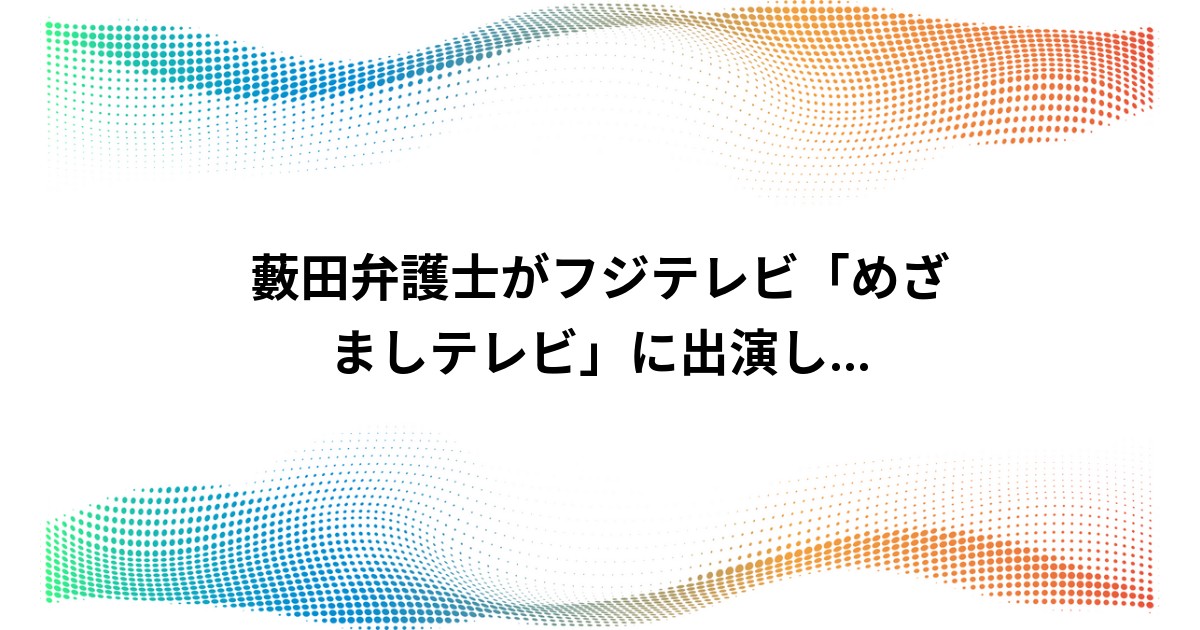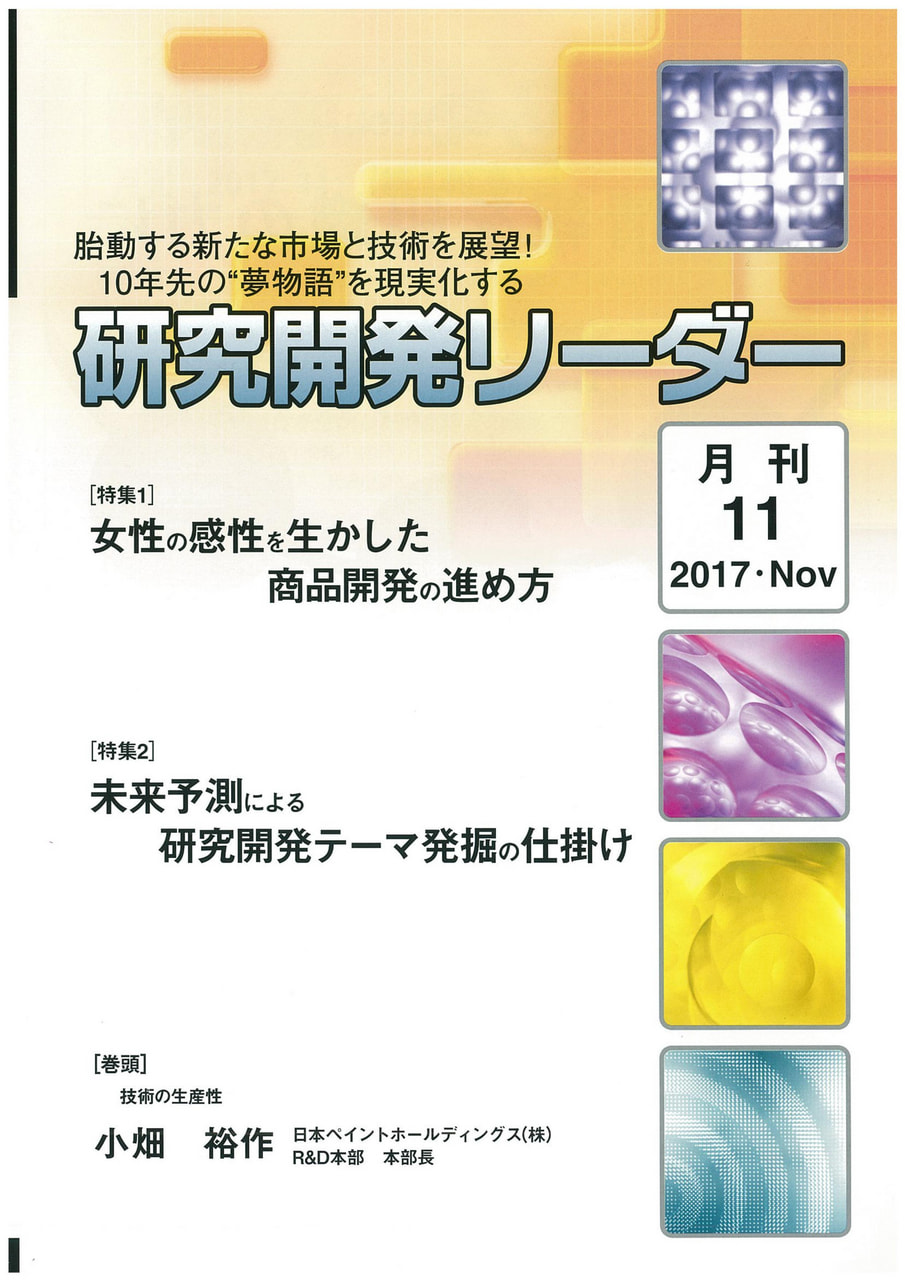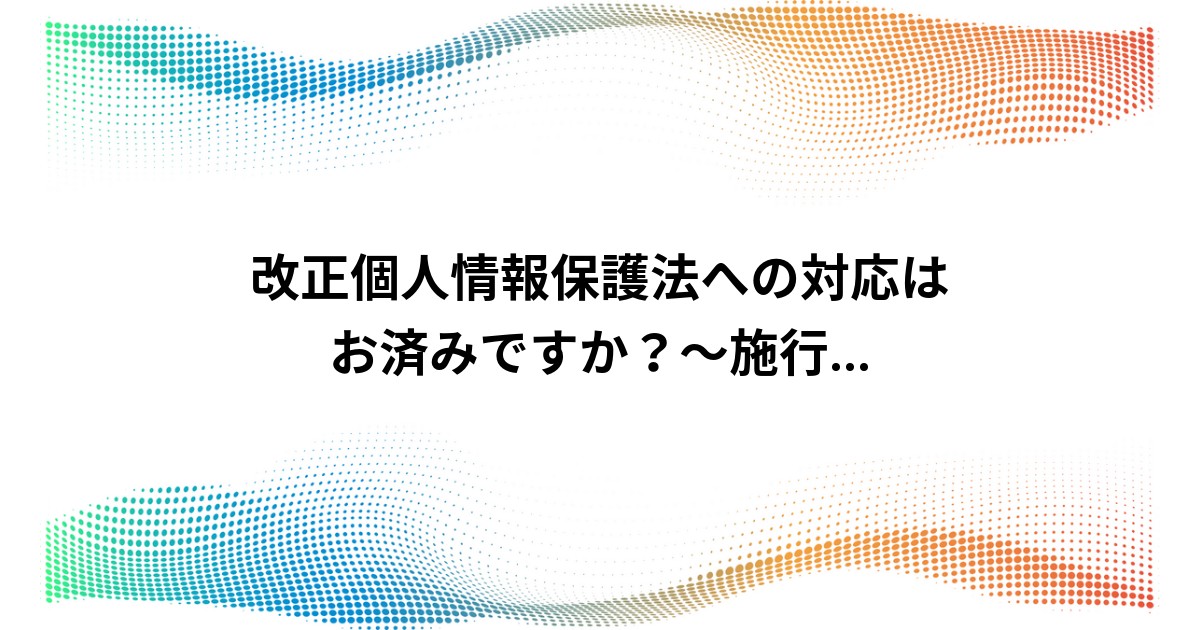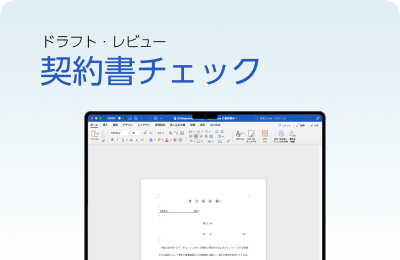Clair Law firm ニュースレター vol.115
弊事務所の近くにある桜も今週になって満開になりました。 今回は、ソーシャルメディアからの情報漏えい防止策と本年4月1日から施行された特定非営利活動促進法(NPO法)の改正を紹介します。 記事に関するご意見やご質問がありましたら、「コメント」欄 https://www.clairlaw.jp/newsletter/ にご記入下さい。当事務所の弁護士がコメントさせて頂きます。みなさんのご意見・ご質問をお待ちしています。 1 ソーシャルメディアからの情報漏えいをどう防止するか 最近、従業員が会社の情報をソーシャルメディア上で公表してしまったというトラブルをよく耳にします。従業員によるソーシャルメディアの利用について、どのような対策を取るべきかを解説します。 2 NPO法の改正について 本年4月1日から施行された特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について解説します。
1 ソーシャルメディアからの情報漏えいをどう防止するか ソーシャルメディアの普及に伴い、従業員がソーシャルメディアを利用して会社の業務に関係する情報を発信し、会社の信用を傷つけるというトラブルが急増しています。 ソーシャルメディアを利用した会社の情報の発信には、 ・情報を発信する機器(スマートフォンなど)が、会社所有のものではなく個人所有のものである ・発信される情報が、会社のサーバではなく発信者(従業員)の頭の中にある という、これまでの情報漏えいのトラブルとは異なった特徴があります。 このため、 ・サーバへのアクセス権の制限やログの管理によって物理的に情報を保護して漏えいを防ぐという方法では対応しきれない ・自分が発信した情報で会社の信用が傷つくかもしれないという意識が低い という問題点があるといわれています。 ソーシャルメディアを利用した会社情報の漏えいを防止するため、少なくとも次の3項目について検討・対応が必要です。 (1)社内規程(就業規則など)にソーシャルメディアを利用する上での制限を設ける、または、ソーシャルメディアの利用に関するガイドラインを制定する。 これは、従業員にルールを明らかにするとともに、ルール違反があった場合に適切に懲戒処分をするという観点からも重要です。 (2)勉強会を開催し、情報漏えいが会社の信用をいかに傷つけるか、理解を深めさせる。 社内規程やガイドラインを変更・制定しても、社員がルールの存在自体を知らない、または内容が難解であったり抽象的であったりしてルールを理解できないのでは情報漏えいを防止することはできません。 このため、社内規程やガイドラインの内容を十分に説明するとともに、実際に発生した情報漏えい事例についての勉強会を定期的に開催し、情報漏えいは規範違反であるとともに、会社の信用をいかに傷つけるかについて、従業員の理解を深めさせることが重要です。 (3)正規従業員だけではなく、パート、アルバイト、委託者、派遣労働者などの非正規従業員にも、ソーシャルメディアを利用した会社情報の漏えいについての理解を深めさせる。 なお、情報漏えいの防止策とあわせて、インターネット上に会社の情報が漏えいし、信用を傷つけかねない事態が生じてしまった場合に備え、次善の策として、被害拡大を防止するための方法を考えておく必要があります。まずは、情報が書き込まれた媒体・日時の特定、証拠の保全、情報の削除などの手順を決めておくとよいでしょう。 また、発信者に対する損害賠償請求に備えて、ソーシャルメディアの運営者などに対し、プロバイダ責任法に基づく発信者情報開示請求を行うことも有用です(佐藤未央)。佐藤未央のなるほど 参考:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項
2 NPO法の改正について 特定非営利活動促進法(NPO法)の一部を改正する法律が、平成24年4月1日に施行されました。 主な改正事項は、設立時の認証制度の見直しと、新認定制度・仮認定制度の導入ですが、今回は設立時の認証制度の見直しについてご紹介します。 (1)活動分野の追加 これまで、特定非営利活動の種類として、17種類の活動分野が認められていましたが、改正により、新たに、3種類追加されました。具体的には、1)「観光の振興を図る活動」、2)「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」、3)「法第2条別表各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動」です。 (2)手続きの簡素化・柔軟化 改正により、株式会社等と同様に、社員総会の決議について、書面等による社員全員の同意の意思表示に替えることができるようになりました(14条の9)。 また、従前は、重要な事項に関する定款変更は、所轄庁による認証及び縦覧手続が設けられていましたが、1)役員の定数、2)会計に関する事項、3)事業年度、4)解散に関する事項のみについての定款変更の場合は、所轄庁への届出のみで足りるように改正されました(25条1項)。 さらに、改正前は、NPO法人としての認証を受ける場合、申請書類を2ヶ月間、公衆の縦覧に供しなければならず、縦覧中、書類に不備があった場合、不備を訂正して再提出した書類を更に2ヶ月間縦覧する必要がありました。改正後は、条例で定める軽微な不備については、申請を受理してから1ヶ月を経過するまでの間に限り、補正を認めることとされました(10条3項)。 (3)未登記法人の認証取消し 以前から、所轄庁からNPO法人設立の認証を受けているものの、登記をしていない法人が少なからず見受けられ、問題となっていました。 このような法人でないNPO団体の存在を解消するため、設立の認証を受けたものが設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても設立の登記をしないときは、所轄庁は認証を取り消すことができるとされました(13条2項)。 上記改正以外にも、税制面の優遇措置も改正されました。財政上の問題を抱えるNPO法人は依然として多くありますので、今回の改正の効果が注目されます(平井)。平井佑治のなるほど 参考:内閣府NPOホームページ https://www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html