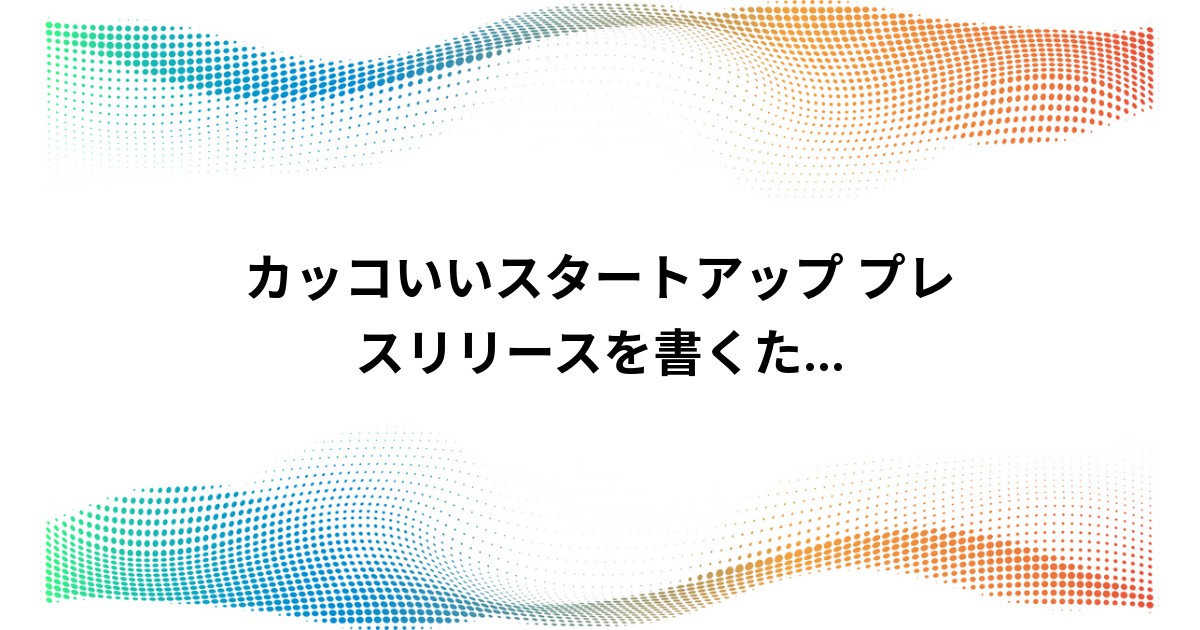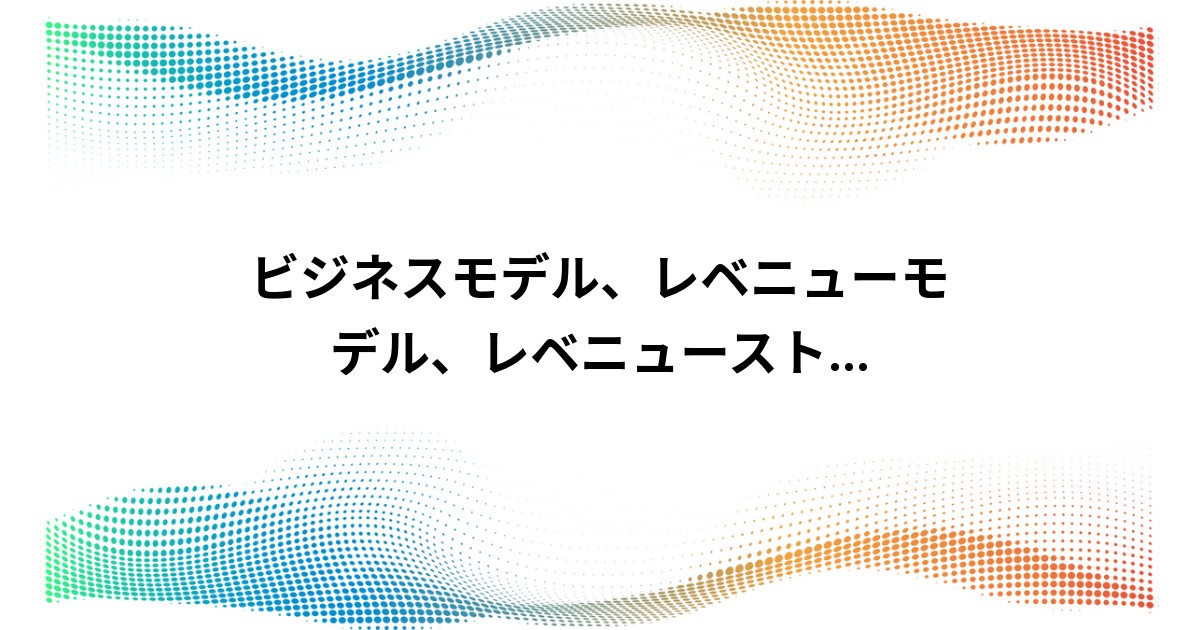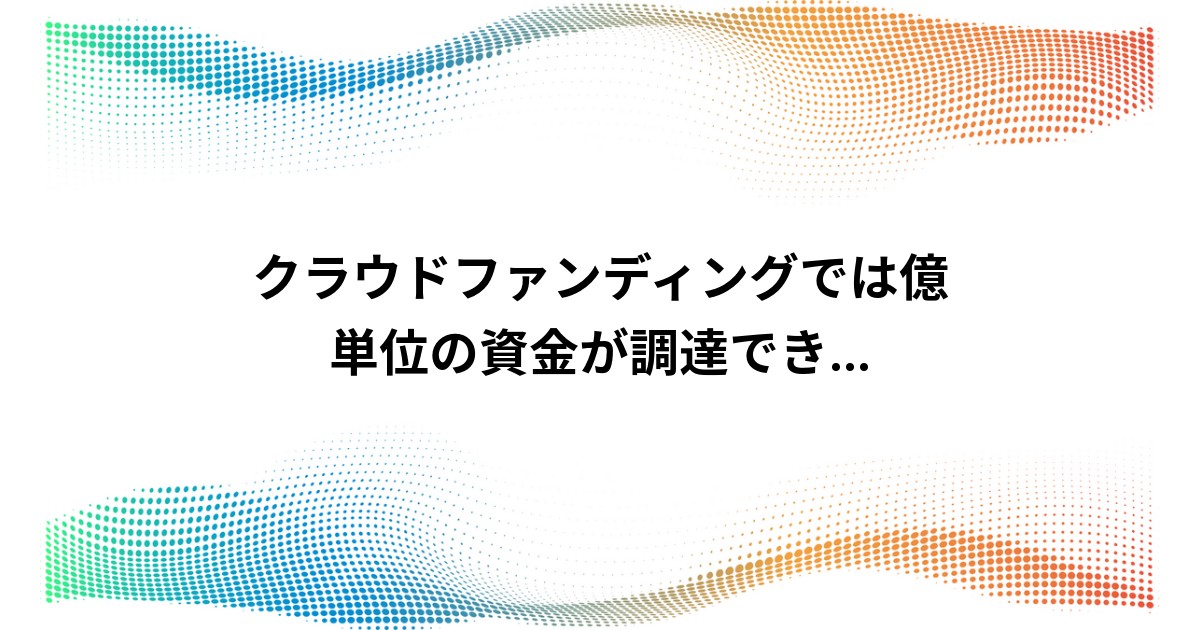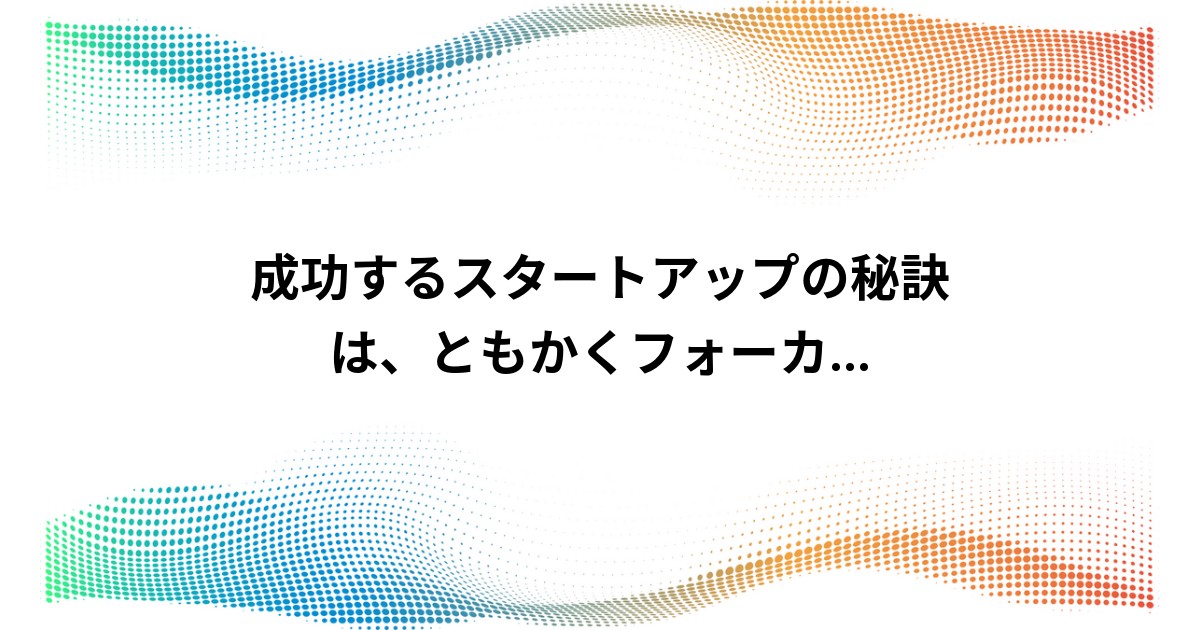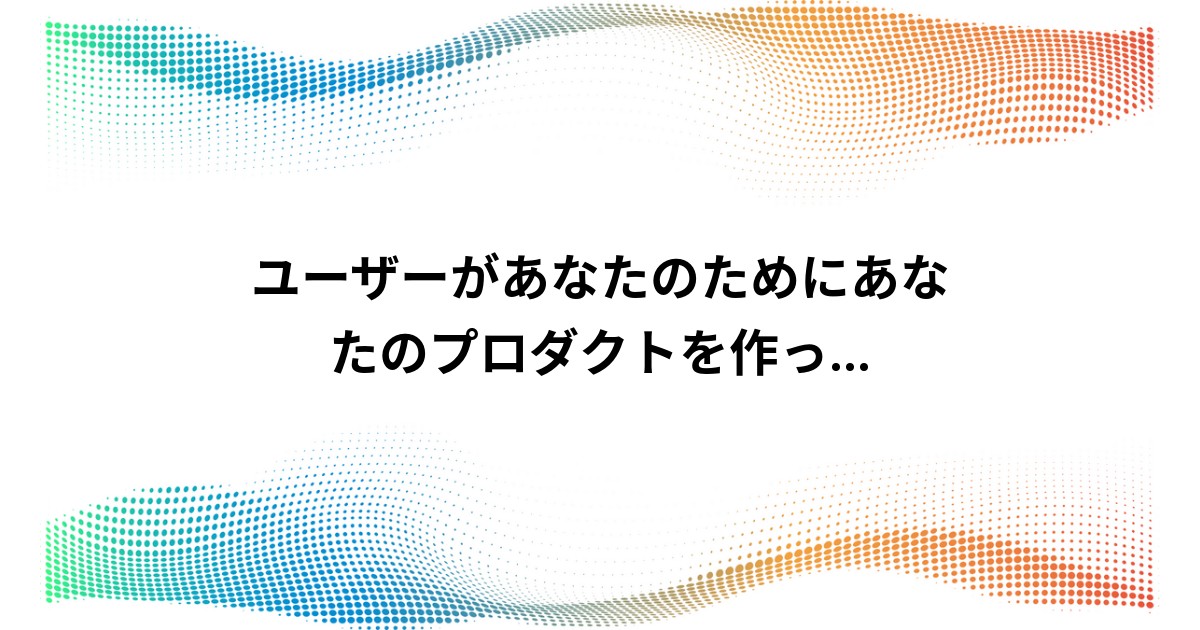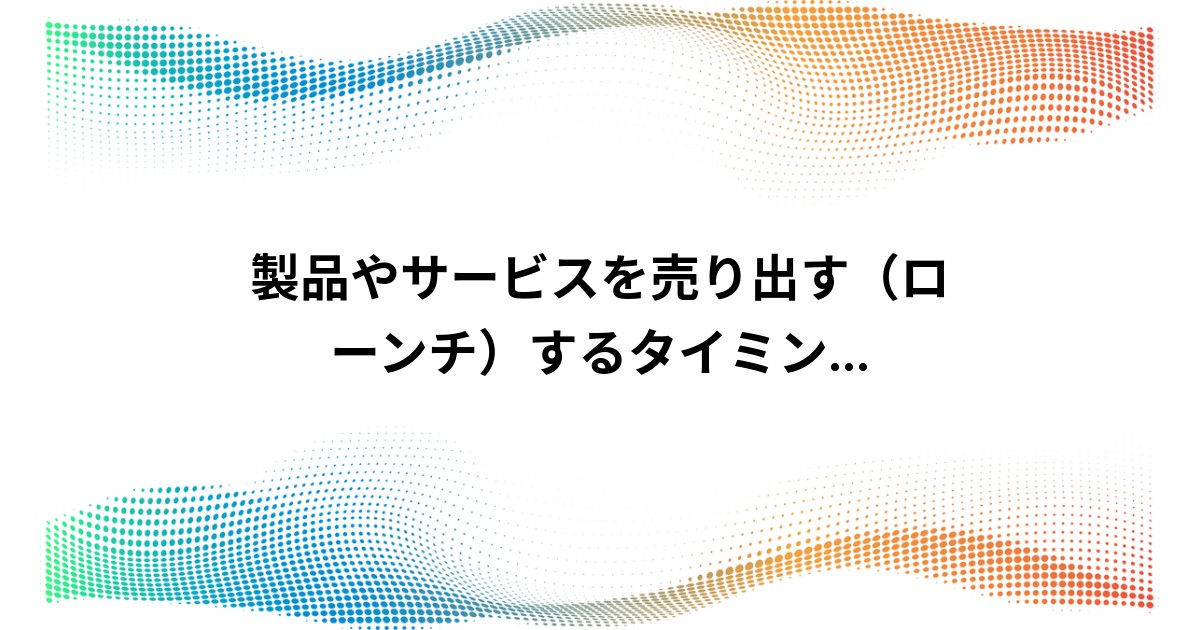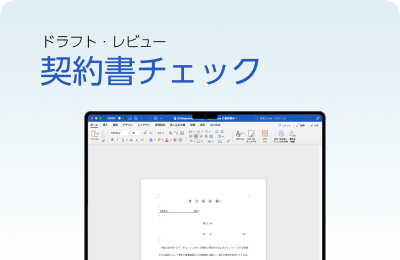Clair Law firm ニュースレター vol.137
今回は、取締役の解任と正当な理由に関する内容と、適格消費者団体について紹介します。 ≪今回のご紹介テーマ≫ 1 取締役の解任と正当な理由 任期途中における取締役の解任に正当な理由ありとされたケースを紹介します。 2 適格消費者団体について 新しい制度として、消費者被害事案の差止等の申立を行う適格消費者団体の制度について 説明します。 3 弁護士Blog情報 所属弁護士による最近のBlog情報を紹介します。
1 取締役の解任と正当な理由 取締役は、株主総会の決議によっていつでも解任できますが(会社法339条1項)、解任され た取締役は、解任に「正当な理由」がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償 を請求することができます(同条2項)。そこで、この「正当な理由」について争われた裁判例を紹介 します。 個人でボイラ工事の仕事を行っていたZは、平成21年5月1日、プロボウラーのXとともに、ボイラ 事業とボウリング事業を目的とするY社を設立しました。このY社の株式はZが全て引き受け、Zが代 表取締役に就任し、Xが取締役に就任しました。 ところが、平成22年10月31日、Y社はXの取締役解任登記をしたため、Xは、Y社に対して 解任に正当な理由がないとして損害賠償を請求しました。 これに対し、Y社は、Xが担当するボウリング事業は、経費を支払ってきたものの売上げは実質ゼロ であったこと、Xはボウリング事業を展開するだけの熱意も能力もなかったことを踏まえ、ボウリング事 業から撤退することに伴いXを解任したのであり、Xの解任には正当な理由があると主張しました。 裁判所は、Xは、Y社のボウリング事業を行うために取締役に就任したのであり、取締役として報酬 を受けたり、Y社に経費を支出させたりする以上は、ボウリング事業の収益があがるよう努力すべきと ころ、Y社にはボウリング事業の売上げはほとんどなく、Xにはボウリング事業を展開する能力がなかっ たものといわざるを得ず、Y社は、このような事情を踏まえてボウリング事業から撤退するとの経営判断 をしたのであり、Xを解任するための正当な理由があったというべきであるとして、Xの請求を棄却しま した。 本事例の他、解任につき「正当な理由」があると認められるケースとして、取締役の職務遂行上の法 令・定款違反行為、心身の故障(最高裁昭和57年1月21日判決)、職務への著しい不適任 などが考えられます。 なお、「正当な理由」がないと判断された場合の損害の範囲は、取締役が解任されなければ在任中 及び任期満了時に得られた利益、つまり得べかりし役員報酬や退職金となります。(佐藤未央)佐藤未央のなるほど 参考:損害賠償請求事件(横浜地裁平成24年7月20日判決) 株主総会決議取消等請求事件(最高裁昭和57年1月21日判決) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66912&hanreiKbn=02
2 適格消費者団体について 消費者契約法では、消費者が誤認・困惑等して締結した契約を取り消すことや、消費者の利益を 不当に害する条項を無効とすること等、消費者に事業者の不正な行為を改めさせることを認めてい ます。 しかし、これらはあくまでも個別対応であり、事業者の不正な行為の拡大を止めるには十分ではあ りません。そこで、2007年に適格消費者団体制度が設けられました。 適格消費者団体は、不特定・多数の消費者に代わって適格消費者団体が事業者の不正な行為 の差止を求めることができる主体となります。個別の契約を取り消したり、契約条項を無効にしたりす るのではなく、不正な行為そのものを差止することで、被害の拡散を防ぐことを目的として設けられた制 度です。 適格消費者団体は、契約締結時に、事業者が、(1)重要事項について事実と異なることを告 げた場合、(2)不確実な事項について断定的判断を提供した場合、(3)不利益な事実を故 意に告げない場合、(4)自宅や職場から退去しない場合、(5)消費者を退去させてくれない 場合や、契約条項として、(6)事業者の損害賠償義務を一切免除する条項、(7)消費者が 支払う損害賠償額として不当に高額なものが設定されている条項、(8)消費者の利益を一方 的に害する条項を設けているような場合に、これらの行為の差止を求めることができます。また、特定商 取引法上の不当な勧誘行為等、景表法上の不当な表示についても差止を求めることができます。 適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。勝手に適格消費者団体で あると名乗っても、不特定・多数の消費者の代わりに差止請求ができるわけではありません。 現在認定されている適格消費者団体は、消費者庁のホームページに掲載されていますので、適 格消費者団体と名乗る団体から、会社に連絡が来た場合は、認定を受けた団体であるかをまず確 認し、適切に対応する必要があります。(吉田南海子)吉田南海子のなるほど 参考 消費者庁「前項の適格消費者団体 消費者の窓」 http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html
3 弁護士Blog情報 中小企業金融円滑化法の期限到来(今月末・平成25年3月)対策 (古田利雄) https://www.clairlaw.jp/blog/toshiofuruta/2013/03/post-25.html
記事に関するご意見やご質問がありましたら、 「コメント」欄 https://www.clairlaw.jp/newsletter/に ご記入下さい。当事務所の弁護士がコメントさせて頂きます。 みなさんのご意見・ご質問をお待ちしています。